結婚式費用で親ともめる経験、実は多くのカップルが通る道なんですよね。
私も結婚式を挙げたとき、親との金銭感覚の違いにびっくり!「なんでそんなにお金をかけるの?」「うちの親戚は全員呼ばないと…」なんて会話が毎日のように。
結論だけをまとめると…
- 親と結婚式費用でもめるパターンは5つの典型的なケースがある
- 援助を受けるかどうかは親の経済状況と自分たちの方針で決める
- 事前の話し合いと明確なルール設定がトラブル回避の鍵
- 援助を断るときは感謝の気持ちを伝えつつ理由を明確に
- 意見の相違が起きたときは優先順位を明確にして交渉する
「親に援助してもらうのは当然」と思っていたのに突然断られたり、逆に「自分たちで準備したい」と思っていたのに親が大きく出てきたり…。
そんな温度差にどう対応すればいいの?と悩んでいませんか?大丈夫です!この記事では、結婚式費用をめぐる親との関係性を上手に築くための具体的な方法をご紹介します。
私自身の経験や多くのカップルの体験談を踏まえて、実践的なアドバイスをたっぷりお届けしますね。
よくある「結婚式費用で親ともめる」5つのパターン

結婚式の準備を進めていくと、親世代との価値観の違いが浮き彫りになることが多いんです。特に費用面では、世代によって「当たり前」の感覚が大きく異なるため、思わぬ衝突が起きがち。
私の友人カップルの多くも、結婚式の準備中に親とのトラブルを経験していました。そんな体験談から見えてきた、典型的な5つのパターンをご紹介します。これを知っておくだけでも、心の準備ができますよ!
両家の援助額の不均衡問題
両家からの援助額に大きな差があると、不公平感が生まれてしまうことがあります。
- 片方の親だけが全額負担し、もう片方は全く出さないケース
- 一方は100万円、もう一方は10万円など、金額に大きな開きがあるケース
- 援助の表明はあったものの、実際には支払われないというトラブル
このようなケースでは、援助が少ない側の親が「義理の親にお世話になっている」という複雑な感情を抱くことも。
逆に援助が多い側の親は「これだけ出しているのだから」と発言権を強く主張するようになり、カップルが板挟みになってしまうんです。
式の規模や会場選びへの干渉
親世代の結婚式に対する考え方は、現代の私たちとはかなり違うことが多いです。
- 「地元の大きなホテルで」と特定の会場にこだわる
- 「親族中心の格式ある式」vs「友人中心のカジュアルな式」の対立
- 予算オーバーの演出や料理を要求される
特に親が費用を負担している場合、「せっかくお金を出すなら自分の希望も通したい」という心理が働きます。
私の場合も、母が「この料理は格安に見えるから絶対ダメ!」と言い出して、予算オーバーの高級コースに変更せざるを得なかったことがありました。結局その差額は自己負担。親心とはいえ、ちょっと複雑な気持ちになりましたね…。
招待客リストをめぐる対立
誰を招待するかという問題は、想像以上に深刻なトラブルになることがあります。
- 親族の招待範囲(いとこまで?親戚一同?)で意見が分かれる
- 「会ったこともない親の知人」を多数招待するよう要求される
- 両家の招待人数バランスが極端に偏る
招待客が増えれば当然費用も増加します。一人当たり2万円以上かかると考えると、「親の知人10人追加」は簡単に20万円以上の出費増に。
友人は「親戚のおじさんたち20人も呼ぶことになって、予算オーバーで大変だった」と嘆いていました。しかも招待客の増加は、会場のグレードアップや引き出物の追加などさらなる出費を招くことに。
「援助するから」という発言権の主張
お金を出している親が「うちが出しているんだから」と強く主張するパターンは非常に多いです。
- 「これだけ出すんだから、この親戚は絶対呼んで」と条件をつける
- 「お金を出すのはこっちなんだから」と決定権を主張される
- 援助額を理由に式の細部まで指示してくる
これは本当に辛いですよね。親の援助はありがたいけれど、そのために自分たちの結婚式が「親のための式」になってしまうというジレンマ。
私の友人は
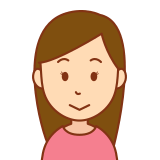
母親が『私のお金で式を挙げるんだから』と毎回言われて、自分の結婚式なのに自分の意見が言えなくなった
と涙ぐんでいました。援助を受ける際は、このリスクも考慮する必要があります。
お金と発言権のバランス崩壊
最も厄介なのが「お金は出さないのに口だけ出す」または「全額出すから全部決める」という極端なケース。
- 費用負担なしに細かい要望だけ主張する親
- 全額負担するから全ての決定権を持ちたがる親
- 「自分たちの時代はこうだった」と時代遅れの常識を押し付ける
どちらも問題の本質は「お金と決定権のバランス」にあります。
援助してくれない場合は自己資金で自由に計画する権利があるはず。逆に全額援助する場合でも、主役はあくまでカップルであることを忘れてはいけません。
これらのパターンを事前に知っておくことで、トラブルの芽を早期に摘み取ることができます。次は、そもそも親からの援助を受けるべきかどうかの判断基準をご紹介しましょう。
結婚式費用で親の援助を受けるor受けないの判断基準
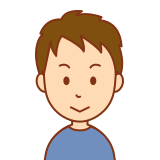
親からの援助、ありがたいけれど受けるべき?
この悩みは多くのカップルが抱えるもの。私自身も「自立した大人として自分たちで払うべき」という思いと、「せっかくの親の好意を無下にしたくない」という気持ちの間で揺れ動きました。
結論から言うと、これは単純に「Yes/No」で決められる問題ではありません。多角的な視点から考慮すべき重要な判断なのです。以下に、判断材料となる要素をご紹介します。
親の経済状況と意向を正確に把握する
まずは親側の状況を正確に理解することが大切です。
- 親が事前に援助の意思を自ら示しているか
- 親の経済状況に実際に余裕があるのか
- 兄弟姉妹の結婚時と同様の扱いになっているか
興味深いことに、ある調査によれば結婚式費用の援助は約85%が親側からの申し出から始まるそうです。親にとって子どもの結婚式への援助は、長年の楽しみだったというケースも多いんです。
私の母は
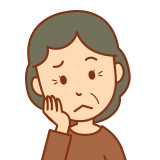
あなたの結婚のために20年前から少しずつ貯めていたのよ
と言ってくれました。そんな長年の思いを受け止めることも、親子関係では大切なことかもしれません。
ただし、親の経済状況を正確に把握することも重要です。表面上は「出せる」と言っていても、実は無理をしているケースもあります。親の退職金や老後資金を使わせるのは、長期的に見て親子関係にも悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
カップルの資金計画と自立の意識
次に、カップル自身の経済状況と意向を考慮します。
- 自己資金で賄える範囲はどこまでか
- 援助なしで式を簡素化する意向があるか
- 借入が必要な場合、返済計画は現実的か
結婚式は確かに特別な日ですが、その後の新生活のスタートにも資金が必要です。「結婚式で全財産を使い切った」というのは賢明な選択とは言えません。
友人のAさんは「親の援助を受けずに自分たちで300万円貯めて式を挙げた」と言っていましたが、その結果「新婚旅行に行けなかった」と後悔していました。
一方、Bさんは「親の援助を一部だけ受け、残りは二人で工面した」というバランスの良い方法を選んでいました。
見積もりを取った上で、どこまでが自分たちの手が届く範囲なのか、冷静に判断することが大切です。
文化的・家族間の慣習を尊重する
地域や家族によって、結婚式に関する暗黙の了解や慣習があることも忘れてはいけません。
- 地域や家柄の慣例(援助が当然視されている風土)
- 両家間のバランス(片方の親のみが援助する場合の調整)
- 結納や婚約食事会などの伝統行事の有無
例えば、地方では「親族中心の格式ある式」が当たり前で、親が全面的に費用を負担するという文化が根強く残っているエリアもあります。そうした背景がある場合、「自分たちだけで」と主張することで、意図せず親を傷つけてしまうこともあるのです。
私の場合は、夫の実家が地方の旧家で「親戚一同を招いて盛大に」という文化がありました。最初は抵抗感もありましたが、結果的に両家の親に一部援助してもらい、それぞれの文化や希望を尊重した形で進めることができました。
心理的負担と親子関係への影響
お金の問題は単なる経済的な話ではなく、心理的な側面も大きいです。
- 援助を受けることでの「借り」の感覚
- 援助額に対する「見返り」の期待の有無
- 親との関係性(金銭的依存が人間関係に影響するリスク)
親からの援助を受けると、無意識に「借り」を感じたり、親の期待に応えなければという心理的プレッシャーを感じることがあります。この心理的負担が大きい場合は、自己資金での開催を検討する方が精神衛生上も良いでしょう。
私の友人は
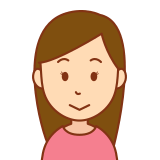
親に全額出してもらったら、その後何年も『あれだけお金かけたんだから』と言われ続けた
と話していました。お金の問題は結婚式当日で終わるわけではなく、その後の親子関係にも影響を及ぼすことを覚えておきましょう。
柔軟な代替案の検討
援助を受けるか否かという二択ではなく、様々な折衷案も検討できます。
- 一時的借入として扱い、ご祝儀で返済する提案
- 部分的な援助のみ受け、残りは自己負担とする案
- 式の規模縮小で必要額を減らす選択
例えば「両親からの援助は新居の頭金に回したい」と伝え、結婚式は小規模にするという選択も可能です。あるいは「ドレス代だけ」「会場費の半分だけ」など、部分的な援助を受けるという方法もあります。
私の友人カップルは「親からの援助はすべてご祝儀から返す」という約束をして援助を受け、実際に式後に全額返済していました。これにより「援助」ではなく「一時的な立て替え」という形になり、心理的負担も軽減されたそうです。
結局、親の援助を受けるかどうかは家族関係や価値観によって大きく異なります。大切なのは、オープンなコミュニケーションを通じて互いの思いを理解し合うこと。そして次に紹介する「話し合いの進め方」も参考にしてみてください。
トラブルを防ぐ!結婚式の費用の話し合いの進め方(5ステップ)

結婚式の費用をめぐるトラブルの多くは、「事前の話し合い不足」が原因です。「言わなくても分かるだろう」という思い込みや「お金の話をするのは気が引ける」という遠慮が、後々大きな問題に発展することも。
私の経験から言えることは、早い段階でしっかりと話し合うことが何よりも重要だということ。以下に、スムーズな話し合いのための具体的なステップをご紹介します。
ステップ1.早期の二人間での予算設定が最優先
まずはカップル間で、お互いの経済状況と結婚式に対する価値観を共有することから始めましょう。
- 収入・貯蓄状況をオープンに共有する
- 「自分たちで賄える範囲」を前提に話し合う
- 総額の上限と、親の援助を期待する金額を明確にする
これは結婚後のお金に関する最初の大きな決断になります。結婚式場を見学する前に、まず「いくらまでなら出せるか」を明確にすることが大切です。
私たちの場合は、エクセルシートを作成し、それぞれの月収、貯蓄額、結婚式に使ってもいいと思う金額を書き出しました。その結果、「二人で200万円までは出せる」という共通認識を持つことができ、その後の会場選びや親との交渉もスムーズに進みました。
具体的な分担方法としては、総額から親の援助額を差し引いた金額を折半する方法や、収入比率に応じた負担配分(例:年収600万:400万なら6:4の割合で負担)なども実践されています。
ステップ2.両家の希望を事前に確認する
親との話し合いは、式場選定前に行うことをおすすめします。
- 援助の有無と金額を明確に確認する
- 式のスタイルに関する希望をヒアリングする
- 招待したい親族・知人のリストを作成してもらう
後から「こんな親戚も呼びたい」「こういう演出もしてほしい」と要望が追加されると、予算オーバーの原因になります。早い段階で親の希望を全て洗い出しておくことが重要です。
私は両家の両親を交えた食事会を設け、そこで結婚式についての希望を聞く機会を作りました。「形式的なことは抜きにして、素直な気持ちを教えてください」と伝えたところ、意外な希望(「友人は呼ばなくていいから親族だけで格式高く」など)が出てきて、初期段階で調整できました。
特に親からの資金援助がある場合は、金額だけでなく使途についても明確にしておくことが必要です。「この金額はドレス代として」「会場費の半分として」など、具体的に決めておくと後のトラブルを防げます。
ステップ3.詳細な費用項目を明確化する
式場との打ち合わせでは、曖昧な部分を残さないことが大切です。
- オプション費用の有無を細かく確認する
- 追加発生しやすい項目(装飾・映像演出など)を把握する
- 支払いスケジュールを書面で確認する
「基本プランに含まれると思っていたら追加料金だった」というトラブルは非常に多いです。見積書の細部まで確認し、不明点はその場で質問することが重要です。
私の場合、最初の見積もりでは省略されていた「会場装花」が後から30万円追加されるという事態に。「てっきり基本料金に含まれていると思った」と言っても後の祭り。こうした「思い込み」によるトラブルを防ぐためにも、細かく確認することを忘れないでください。
アイテム別に負担を分ける方法(例:挙式費用は折半、衣装代は各自負担)も効果的です。特に「こだわり」の部分は、希望する側が多めに負担するというルールを設けると、話し合いがスムーズになります。
ステップ4.柔軟な分担ルールを設定する
厳密な折半にこだわらず、状況に応じた柔軟なルール作りが大切です。
- 収入比率に応じた負担配分を検討する
- こだわりアイテムは希望者が多めに負担する
- 予算超過リスクへの対応を事前に合意しておく
例えば、新郎新婦の収入差が大きい場合、単純な折半ではなく収入比率に応じた負担にするとバランスが取れます。また「ビデオ撮影は新婦側が希望するから新婦側負担」「和装は新郎側の希望だから新郎側負担」というように、希望する側が負担するというルールも有効です。
実際に私たちは、以下のような表を作成して分担を決めました。
| 項目 | 総額 | 新郎負担 | 新婦負担 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 会場費 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 折半 |
| ドレス代 | 30万円 | 0円 | 30万円 | 新婦側希望で上位プラン選択 |
| 映像制作 | 15万円 | 15万円 | 0円 | 新郎側希望 |
| 引出物 | 20万円 | 親族分(12万) | 友人分(8万) | 招待者に応じて分担 |
このように視覚的に整理すると、「不公平感」も解消されやすくなります。
ステップ5.定期的な見直しと情報共有を徹底する
準備段階で費用は変動するものです。定期的な確認と共有が欠かせません。
- エクセルなどで費用管理表を作成し共有する
- ゲスト数増加時には必ず再計算する
- オプション追加時にはその都度共有し合意を得る
「言ったはず」「聞いていない」というコミュニケーション不足によるトラブルを防ぐためにも、変更があるたびに書面で確認する習慣をつけましょう。
友人カップルはGoogle スプレッドシートで費用管理表を作り、お互いがいつでも確認・編集できるようにしていました。これにより「知らなかった」というトラブルを防ぎ、予算管理も容易になったそうです。
特にゲスト数の増加は、料理代・引出物・席札など様々な費用に直結します。「親戚1人追加」と聞くと小さな変更に思えますが、実際には2万円以上のコスト増になることも。こうした変動要素も含めて、定期的な見直しが必要です。
これらのステップを踏むことで、金銭面のストレスを軽減し、より良い結婚式準備が可能になります。次は、親からの援助を丁寧に断る方法についてご紹介します。
結婚式費用の援助の断り方(角が立たない言い方例)
親からの援助を断るのは、思っている以上に繊細な問題です。「せっかくの好意を無下にするのは申し訳ない…」という気持ちと「自分たちのやりたいようにしたい」という思いの狭間で揺れ動くことも多いでしょう。
私自身も義母からの「ドレス代は全部出すわ」という申し出に、「ありがたいけれど自分たちで」と断るのに苦労しました。感情を傷つけずに断るには、いくつかのコツがあります。以下に具体的な方法をご紹介します。
感謝の気持ちを最優先に伝える
まずは親の好意に対する感謝の気持ちをしっかりと伝えることが大前提です。
- 「ご厚意は本当にありがたいです」と謝意を示す
- 「お心遣いに感謝しています」と親の気持ちを尊重する
- 「とても嬉しい申し出です」と喜びを素直に表現する
断る前に必ず感謝の言葉を述べることで、親は「自分の気持ちが否定されている」という印象を受けにくくなります。クッション言葉として「ご厚意は大変ありがたいのですが」「お心遣いに本当に感謝しています」などを使うと、後に続く断りの言葉も受け入れられやすくなります。
私の友人は、父親からの援助を断る際に
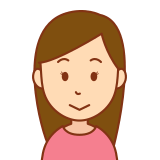
パパが娘のために用意してくれたお金、本当に嬉しいよ。こんなふうに考えてくれていたなんて、幸せな娘だなって思った
と伝えてから断りの言葉を続けたそうです。父親は少し寂しそうにしながらも、「そうか、分かった」と受け入れてくれたとか。
感情に訴えかける言葉は、特に親子関係では効果的です。「あなたの気持ちが嬉しい」という部分を強調しましょう。
明確な理由を簡潔に伝える
断る理由は、できるだけ具体的かつ簡潔に伝えることが重要です。
- 「既に自分たちで費用を準備しています」と事実を伝える
- 「兄夫婦との公平性を重視したい」と家族の事情を説明する
- 「大人として自立したい気持ち」を素直に表現する
曖昧な説明や抽象的な理由よりも、具体的で明確な理由を伝える方が説得力があります。特に「すでに準備している」「他の兄弟との公平性」「自立の意思」などは、親も理解しやすい理由です。
私の場合は「義母さんのご厚意は本当にありがたいのですが、私たちの結婚式は自分たちの力で作り上げたいという思いがあります。これから夫婦として歩んでいく最初の一歩として、自分たちの手で準備したいんです」と伝えました。具体的な価値観を説明することで、理解を得ることができました。
一貫性のある主張も重要です。「今回は遠慮したい」と伝えておきながら、後で「やっぱり援助してほしい」と言うと信頼を損ねてしまいます。断る際は、本当にその決断で良いのか、パートナーとしっかり話し合っておきましょう。
具体的な断り方の例文パターン
実際の会話では、どう切り出していいか迷うことも多いでしょう。以下に状況別の例文をご紹介します。
- 公平性を重視する場合の断り方
- 経済的自立を伝える場合の断り方
- 代替案を提示する場合の断り方
公平性を重視する場合
「お母さんのご厚意は本当に嬉しいです。ただ、義兄夫婦が自分たちで資金を用意していたこともあり、私たちも同じように自分たちの力でやりたいと思っています。もし同じように援助をいただくと、義兄夫婦に申し訳ない気持ちになってしまうんです。どうかご理解いただけますと幸いです。」
経済的自立を伝える場合
「パパの気持ち、本当にありがたいです。でも、私たちはこの結婚式を二人の力で作り上げたいと思っているんです。二人で貯金をしてきたこともあり、自分たちの手で準備することに意味を感じています。温かく見守っていただけると嬉しいです。むしろ当日、親としての姿を誇らしく感じてもらえる式にしたいんです。」
代替案を提示する場合
「お義父さん、そんなに気にかけていただいて感謝しています。実は結婚式の費用は既に私たち二人で計画を立てているんです。でも、もしお気持ちをいただけるなら、新生活の家具購入や将来の住宅資金として大切に使わせていただきたいと思います。そちらの方が私たちには大きな助けになるんです。」
心を込めた感謝の言葉と具体的な理由を組み合わせることで、親も理解しやすくなります。
注意点と気をつけるべきポイント
援助を断る際には、いくつか気をつけるべきポイントがあります。
- 曖昧な表現は避け、明確に意思を示す
- 両親やパートナーとの事前連携を徹底する
- 感情的にならず、冷静に伝える
「検討します」「考えておきます」という曖昧な返事は、親に期待を抱かせてしまう原因に。はっきりと「ありがたいですが、お断りしたいと思います」と意思表示することが大切です。
また、パートナーや両親との連携も重要なポイント。片方の親には断り、もう片方からは援助を受けるという場合、両親同士で話し合った際に「うちは援助したのに、あちらは断られた」といった誤解が生じかねません。両家での情報共有と方針統一を心がけましょう。
友人は「夫に『お母さんの援助は断ったよ』と伝えずにいたら、夫が『うちの親は全部出してくれるって』と私の親に言ってしまい、大変なことになった」と苦い経験を語っていました。パートナーと常に情報を共有し、足並みを揃えることが重要です。
感情的にならず冷静に伝えることも大切。親の申し出を「余計なお世話」と感じても、そのような言い方は避け、感謝の気持ちを基調にした丁寧な断り方を心がけましょう。
援助を断る際は、言葉選びに気を配りながらも、自分たちの意思をはっきりと伝えること。そして何より、親の気持ちを尊重する姿勢を忘れないことが大切です。次に、もし親と意見が合わない場合の対処法について見ていきましょう。
結婚式費用で親と意見が合わないときの対処法

結婚式の準備は、世代間の価値観や優先順位の違いが顕著に現れる場面です。「なぜそんなお金をかけるの?」「親戚は全員呼ぶべき」など、親との意見の相違は珍しくありません。
私自身、母が「ウェディングケーキは絶対に必要」と主張し、私が「ケーキカットの演出はしたくない」と思っていた時には、かなり険悪な雰囲気になったことがあります。でも、いくつかの方法を試すことで、最終的には双方が満足する形で解決できました。
以下に、親と意見が合わない際の効果的な対処法をご紹介します。
事前の話し合いと優先順位の明確化
問題が大きくなる前に、早い段階で方針を明確にしておくことが重要です。
- 両家の意見を早期にすり合わせる
- 新郎新婦で「絶対に譲れないポイント」をリスト化する
- 親が重視するポイントを事前に把握する
式場選びや予算策定の初期段階で、親が重視するポイント(日取り・ゲスト数・形式など)を確認しておくことで、後々の衝突を防ぐことができます。
また、カップル自身も「絶対に譲れないポイント」と「妥協できる部分」を明確にしておくことが大切です。すべてにこだわると収拾がつかなくなるので、優先順位をつけて交渉に臨みましょう。
私たちの場合は、「料理のグレード」「写真撮影」「会場の雰囲気」を最重要項目とし、「引出物」「装花」「演出」は親の意見も取り入れる形で進めました。この優先順位を明確にしておくことで、親との交渉もスムーズになりました。
費用分担の公平なルール設定
お金と決定権のバランスは常に意識すべき重要なポイントです。
- 人数割りと折半の併用で不公平感を解消
- 援助金の共通口座管理で透明性を確保
- 決定権と費用負担のバランスを取る
ゲスト数に差がある場合、料理・ギフトなど人数比例部分は「人数割り」、装花・ビデオなど共通費用は「折半」で清算する方法が効果的です。この方法なら「親戚が多い側が余計に負担する」という公平性が保たれます。
両家からの援助金は、全額を共通口座に入れて結婚式全体の費用として扱うことで、「このお金はどちらのもの」という区別をなくすことも有効です。援助額に差がある場合は、多く援助した側が特定の演出を決める権利を得るなど、バランスを取る工夫も検討できます。
友人カップルは「両家の援助額は公表せず、全て共通予算として扱う」というルールを設けることで、金額の差によるトラブルを回避していました。また「両家それぞれに『決められる項目』を振り分ける」という方法も効果的だったそうです。
親との建設的な対話テクニック
親との話し合いでは、対立ではなく建設的な対話を心がけましょう。
- 「イエスアンド話法」で代替案を提示する
- 経済事情を率直に開示して理解を求める
- 親の意見を否定せず、共感点を見つける
親の意見を真っ向から否定するのではなく、「そうですね、それなら〜という案もどうでしょうか」と代替案を提示する「イエスアンド話法」が効果的です。まずは親の意見を肯定した上で、自分たちの考えを付け加えるのがポイントです。
例えば「格式高い料理が必要」と主張する親に対して、「格式は大切ですよね。それなら料理はグレードアップして、その代わり装花は簡素にするのはどうでしょう?」と提案する方法です。
また、経済事情を率直に開示することも有効です。「この演出を加えると予算が〇万円オーバーします」と具体的な数字で示すことで、親も現実的な判断ができるようになります。
私の場合、母の「ウェディングケーキは必要」という主張に対して「確かに素敵な演出ですよね。でも実は私たち、デザートビュッフェにこだわりたいと思っていて、両方だと予算オーバーなんです」と伝えたところ、「じゃあ小さなケーキだけにして、デザートを充実させれば?」という妥協案が生まれました。
第三者を活用した客観的調整
時には、第三者の力を借りることも効果的です。
- ウェディングプランナーに相談して中立な提案を得る
- 書面での可視化で不公平感を解消する
- 第三者の経験談を参考にする
カップルと親の間で意見が対立したとき、ウェディングプランナーなどの専門家を交えることで、客観的な視点からの提案が可能になります。「プロから見てどうですか?」と聞くことで、親も納得しやすくなるでしょう。
また、予算や分担比率を表にまとめるなど、書面で可視化することも効果的です。感情的な議論よりも、数字やプランを具体的に示すことで、冷静な判断につながります。
友人は「両親を交えた打ち合わせで意見がまとまらない時、ウェディングプランナーに『最近の一般的な傾向はどうですか?』と質問したら、親も納得してくれた」と話していました。第三者の意見は、感情的になりがちな親子間の議論を和らげる効果があります。
資金依存度のコントロール
決定権と資金提供のバランスを意識することも重要です。
- 親への依存を最小限に抑え、口出しを防ぐ
- 衣装代など個別費用は各自負担とする
- 援助が多い項目と少ない項目を明確に区分する
「お金を出している=すべてを決める権利がある」という考え方は避けるべきです。むしろ、援助を受ける項目と自己負担の項目を明確に分けることで、決定権の所在も明確になります。
例えば「会場費は親に援助してもらうが、演出や衣装は自己負担」と決めれば、演出や衣装については自分たちの意思で決められます。逆に、親が全額負担する項目については、親の意向も尊重する姿勢が大切です。
私の友人カップルは「親からの援助は会場費と料理代のみに限定し、その他の演出や装飾は全て自己負担」というルールを設けたことで、「基本は親の希望を聞き、こだわりの部分は自分たちで決める」というバランスを取ることができたそうです。
これらの対策を組み合わせることで、金銭トラブルを予防しつつ、親の気持ちも尊重した結婚式準備が可能となります。何よりも大切なのは、オープンなコミュニケーションと相互理解です。
「結婚式費用で親ともめる」のまとめ
結婚式費用をめぐる親との対立は、多くのカップルが経験する道です。でも、事前の準備と適切なコミュニケーションがあれば、大きなトラブルに発展せずに済みます。
この記事で紹介してきた内容を振り返ると、親との関係を良好に保ちながら結婚式を成功させるポイントが見えてきます。
- 親ともめる典型的なパターンを理解し、事前に対策を講じる
- 援助を受けるかどうかは多角的な視点から判断する
- 費用の話し合いは早期に、具体的に、透明性を持って進める
- 援助を断る際は感謝の気持ちを伝えつつ理由を明確にする
- 意見の相違が起きた時は優先順位を明確にして冷静に交渉する
結婚式費用で親ともめる状況は、時に感情的になりがちです。でも、こうした経験は実は「新しい家族の形成過程」でもあるんですよね。
親は子どもの幸せを願い、カップルは自分たちらしい式を挙げたい。その思いがぶつかり合うのは、ある意味自然なこと。大切なのは、互いの思いを尊重しながら、どう折り合いをつけていくかという過程です。
私自身も含め、多くの先輩カップルの経験から言えることは、「早めの話し合い」「明確なルール設定」「優先順位の明確化」の3つが特に重要だということ。この点を意識するだけでも、多くのトラブルを避けることができます。
それから、忘れてはならないのは「感謝の気持ち」です。親からの援助を受ける場合も断る場合も、まずは親の気持ちに感謝することから始めましょう。
結婚式費用で親ともめる経験は、実は結婚生活におけるお金の話し合いの良い練習になります。この経験を通して、パートナーとのコミュニケーション力も高まるはず。
素敵な結婚式と、その先の幸せな結婚生活のために、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。最後に、どんな結婚式であれ、それはあなたたち二人の新しい出発点。親との関係も大切にしながら、二人らしい一日を創り上げてくださいね。




















コメント