結婚式を黒字にするのはおかしいと思っている方、こんにちは。
私も数年前に結婚式を挙げた経験があるので、「ご祝儀で得するなんて…」という気持ち、とてもよく分かります。
結婚式の収支って、なんだか触れにくい話題ですよね。
でも、以下の点を追求しつつ、あなたの疑問や不安に寄り添いたいと思います。
- 結婚式を黒字にすることの「おかしさ」や倫理的な問題点
- そもそも黒字化は現実的に可能なのか
- 黒字化するための具体的な方法
- 最終的には両方の価値観の問題
この記事では、これらの点について私の経験も交えながら丁寧に解説していきます。
あなたが心からの選択ができるよう、一緒に考えていきましょう。
結婚式を黒字にするのはおかしい?「おかしい」と感じる理由と価値観の問題

「結婚式でお金もうけ?」と違和感を覚える方は少なくありません。
私自身、友人の結婚式に出席するたび「このご祝儀、どう使われるのかな」と考えることがあります。
結婚式の黒字化に対して「おかしい」と感じるのは、以下の3つの理由からですね。
- 本来の結婚式の意義とのギャップ
- ゲストへの感謝や敬意の問題
- 文化的・社会的な価値観との衝突
それぞれの視点から掘り下げてみましょう。
本来の結婚式の意義とのギャップ
結婚式って本来、何のための場なのでしょうか?
新郎新婦が愛を誓い合う神聖な儀式であり、家族や友人に感謝を伝える場です。
それなのに、黒字化を意識するあまり「いかにコストを抑えるか」「いくらご祝儀が集まるか」といった計算が前面に出ると、本来の意義が薄れてしまいます。
私の友人は
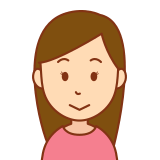
コスト計算ばかりしていたら、当日の感動が半減した
と後悔していました。
結婚式は一生の思い出なのに、損得勘定で台無しにしてしまうのは、やはりおかしいと感じる方は多いのではないでしょうか。
感謝を伝える場が「ビジネスライク」になってしまうのは、なんだか本末転倒な気がします。
ゲストへの感謝や敬意の問題
ご祝儀は、ゲストが新郎新婦への祝福の気持ちを形にしたものです。
「あなたたちの門出を祝いたい」「幸せになってほしい」という温かい思いが込められています。
それを「収入源」として捉えると、ゲストの善意を軽んじているような印象を与えかねません。
私の結婚式では、遠方から来てくれた友人が
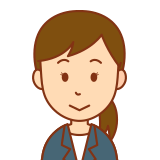
交通費と宿泊費かかったけど、あなたの晴れ姿が見れて嬉しかった
と言ってくれました。
そんな思いを経済的な計算に置き換えるのは、やはり違和感があります。
黒字を出すために料理や引き出物の質を下げてしまうと、「おもてなし」の心が疎かになる可能性も……。
せっかく時間を割いて祝福してくれるゲストへの配慮が薄れてしまうのは、やはり問題です。
文化的・社会的な価値観との衝突
日本の伝統的な価値観では、結婚式は「家と家の結びつき」を社会に報告する場でもありました。
そのため、特に年配の方々は「ご祝儀を利益として考えるのは失礼」と感じる傾向が強いようです。
私の母も
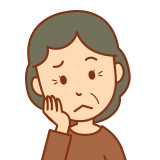
ご祝儀は新生活のための支援であって、利益ではない
と強く主張していました。
世代間の価値観の違いが、こうした「おかしさ」の感覚を生み出す一因になっているのかもしれません。
結婚式にかけるお金は「浪費」ではなく「必要な社会的儀礼への投資」と考える文化的背景があるのです。
どちらが正しいというわけではありませんが、こうした価値観の違いを理解することは大切です。
そもそも結婚式を黒字にすることは可能?

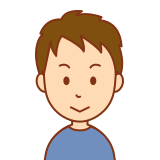
結婚式を黒字にするなんて、本当にできるの?
という疑問をお持ちの方も多いと思います。
ある調査によると、実際に黒字化を達成できるカップルは全体の2割以下程度なんだそうです。
つまり、決して簡単なことではないということ。
でも、以下のような工夫次第では可能性はあります。
- 黒字化の基本原理と計算式
- 黒字化しやすい条件とは
- 実現のためのポイント
それぞれ詳しく見ていきましょう。
黒字化の基本原理と計算式
結婚式の収支は、シンプルに言えば「総費用 - ご祝儀総額 = 自己負担額」という計算式になります。
この自己負担額がマイナスになれば、黒字ということになりますね。
私の結婚式のときは、この計算式をエクセルで作って、逐一シミュレーションしていました。
とはいえ、実際には様々な要素が関わってきて、予想通りにはいかないことも多いです。
例えば、招待状を送ったゲストが全員出席するとは限りませんし、ご祝儀の金額も人によって差があります。
また、当日の急なトラブルで追加費用が発生することも……。
だからこそ、現実的な計画が必要なんです。
黒字化しやすい条件とは
黒字化しやすい条件はいくつかあります。
まず、ゲスト数が適正規模であることが重要です。
専門家によると、80~100名程度の規模が最も黒字化しやすいといわれています。
これは固定費(会場費や衣装代など)を多くの参加者で分散できるからです。
私の友人は100名の披露宴を開き、会場費や衣装代などの固定費を上手くゲスト数で割ることで、一人当たりのコストを抑えることができました。
また、オフシーズンや平日を選ぶことも効果的です。
冬の平日なら、会場費が最大50%近く割引になる場合もあるんですよ。
さらに、ゲスト一人当たりの費用を3万円以下に抑えることも重要なポイントです。
ご祝儀の相場が3万円程度であることを考えると、これ以上コストがかかると黒字化は難しくなります。
実現のためのポイント
黒字化を実現するための具体的なポイントはいくつかあります。
まず、持ち込み可能なものは積極的に活用しましょう。
例えば、引き出物を持ち込むだけで費用を30%ほど削減できることもあります。
私の場合は、招待状を手作りすることで、予算の5%ほど節約できました。
また、ブライダルフェアに積極的に参加することも有効です。
複数の会場を見学すると、商品券やギフト券がもらえることが多く、それを結婚式の費用に充てることができます。
友人のケースでは、7か所の式場見学で合計8万円分のギフト券を獲得していました。
さらに、衣装は新品購入ではなくレンタルや中古品を検討すると、大幅に費用を抑えられます。
ただし、こうした工夫をする際も「おもてなしの質」とのバランスを考えることが大切です。
あまりにも節約に走ると、ゲストの満足度が下がり、結果的に思い出にも影響します。
結婚式を黒字化する具体的な計画

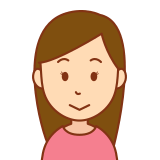
じゃあ具体的にどうすればいいの?
と思われた方のために、黒字化のための具体的な計画を考えてみましょう。
私の経験と友人たちの体験をもとに、実践的なアドバイスをまとめました。
- 予算計画の策定と費用構造の把握
- ゲスト戦略と招待人数の決定
- 具体的な費用削減策
- 契約前の交渉と注意点
一つずつ見ていきましょう。
予算計画の策定と費用構造の把握
まず最初に行うべきは、詳細な予算計画の策定です。
結婚式の費用は大きく分けて「固定費」と「変動費」に分類できます。
固定費には会場費、衣装代、写真・映像費などが含まれます。
一方、変動費は料理代、ドリンク代、引き出物などゲスト数に比例して増える費用です。
私の結婚式では、最初に全体予算の上限を決め、そこから逆算して各項目の予算を設定しました。
特に重要なのは、一人あたりの費用を明確に計算することです。
例えば、料理は一人あたり1万円、ドリンクは3千円、引き出物は5千円といった具合に、細かく設定していきます。
ご祝儀の相場(3万円前後)を考慮すると、ゲスト一人当たりの総費用を3万円以下に抑えることが黒字化の鍵です。
また、予想外の出費に備えて、総費用の10%程度は「余裕/予備」として確保しておくことをおすすめします。
私の場合、当日のちょっとしたトラブルで追加費用が発生し、この余裕が本当に役立ちました。
ゲスト戦略と招待人数の決定
ゲスト数は黒字化に大きく影響します。
先ほども触れたように、80~100名程度の規模が最も効率的といわれています。
少人数婚(30人程度)の場合は、固定費の負担が大きくなるため、演出を簡素化するなどの工夫が必要です。
逆に大規模婚(100名以上)では、会場の規模拡大に伴うコスト増加に注意が必要です。
私の友人は、当初150名規模の披露宴を計画していましたが、費用シミュレーションした結果、90名に絞ることで黒字化を実現しました。
また、ゲストリストを作成する際は、関係性や年齢層を考慮することも大切です。
一般的に親族や上司などは、友人よりも多めのご祝儀を包む傾向があります。
ただし、ゲスト選びを「ご祝儀の金額」だけで判断するのは本末転倒です。
祝福してほしい大切な人を招待することを第一に考えましょう。
出席率については80%程度を見込んでおくと、過剰な準備を避けられます。
>>>関連記事

具体的な費用削減策
費用削減のためのテクニックはたくさんあります。
まず、式場選びの際は、オフシーズン(1~3月)や平日を選ぶことで、20~30%の割引が期待できます。
私の結婚式は2月の平日で、通常より25%安く会場を抑えることができました。
料理については、コース内容を見直したり、ドリンクメニューを調整することで、一人あたり5,000円程度の節約が可能です。
友人は、デザートビュッフェを省略することで、一人あたり2,000円のコストカットに成功していました。
演出面では、プロの司会者ではなく友人に依頼したり、生演奏ではなくプレイリストを活用することで、10~20万円の削減が見込めます。
また、装飾類も手作りすることで大幅に費用を抑えられます。
私はテーブル装花を手作りし、プロに依頼するよりも7割ほど安く済ませることができました。
衣装については、レンタルや中古品を利用すると、新品購入に比べて50%程度節約できます。
さらに、式場見学キャンペーンを利用することで、電子マネーやギフト券を獲得できることもあります。
友人は8つの式場を回り、合計で10万円分のポイントを獲得していました。
契約前の交渉と注意点
式場との契約前の交渉も、黒字化のために重要なポイントです。
まず、見積書の詳細をしっかりと確認し、不要なオプションを削除するよう交渉しましょう。
例えば、高級フォトブースやプレミアムドリンクなど、なくても問題ないサービスもあります。
また、持ち込み可能なアイテムの範囲を広げてもらうことも交渉のポイントです。
引き出物や装飾品を外部から調達することで、式場のマージンを回避できます。
私は写真撮影を外部のカメラマンに依頼することで、式場のプランより15万円安く済ませることができました。
さらに、追加特典として挙式時間の延長やドレスチェンジ回数の増加などを要求するのも効果的です。
ただし、交渉の際は礼儀正しく、無理な要求はしないように注意しましょう。
また、キャンセルポリシーや追加費用の発生条件なども事前に確認しておくことが大切です。
友人は直前になって追加費用が発生し、予算オーバーになってしまったという苦い経験をしています。
契約前に全ての条件を明確にしておくことで、そうしたトラブルを避けられます。
結婚式の黒字を目指すも赤字を受け入れるのもその人(カップル)次第
結局のところ、結婚式を黒字にするか赤字を受け入れるかは、カップルの価値観や優先事項によって決まります。
どちらが正解というわけではなく、二人が納得できる形を選ぶことが最も大切です。
私たちの場合は、ほぼトントンになりましたが、それは偶然であって、最初から目指していたわけではありませんでした。
- それぞれの選択のメリットとデメリット
- 価値観の違いと向き合い方
- 後悔のない結婚式のために
最後に、この点についても考えてみましょう。
それぞれの選択のメリットとデメリット
黒字を目指す場合のメリットは、何と言っても経済的な負担の軽減です。
新婚生活や新居の購入、新婚旅行など、結婚後にはお金がかかることが多いもの。
結婚式で黒字が出れば、そうした費用に回すことができます。
私の友人は結婚式の黒字分で家具を揃えることができたと喜んでいました。
一方、デメリットとしては、費用削減にこだわりすぎると、理想の結婚式から妥協しなければならない点が挙げられます。
特にゲストへのおもてなしの質が低下すると、後々「もっと良いものを用意すれば良かった」と後悔する可能性も。
赤字を受け入れる場合は、理想の結婚式を追求できるというメリットがあります。
思い出に残る特別な演出や、ゲストに喜んでもらえる料理や引き出物にこだわることができます。
私の姉は「一生に一度だから」と割り切って赤字覚悟で結婚式を挙げ、今でも「あの選択で良かった」と言っています。
デメリットは、もちろん経済的な負担が大きくなること。
特に新婚生活のスタートに当たって、大きな出費は避けたいというカップルも多いでしょう。
価値観の違いと向き合い方
結婚式に対する価値観は、人それぞれ異なります。
「一生に一度の思い出だからお金をかけたい」と考える人もいれば、「シンプルで費用を抑えたい」と考える人もいます。
夫婦間で価値観が異なることも珍しくありません。
私の場合、夫は「シンプルに」と考え、私は「特別な日だから」とこだわりがありました。
こうした価値観の違いをどう調整するかが、結婚式準備の大きな課題になることも。
大切なのは、お互いの価値観を尊重し、二人が納得できる妥協点を見つけることです。
例えば、衣装にはこだわるけれど演出は簡素にするなど、優先順位をつけて話し合うと良いでしょう。
また、両家の親の意見も影響することが多いです。
特に年配の方は「ご祝儀で黒字を出すなんて」と抵抗感を持つことも。
そんなとき、なぜそう考えるのかをしっかり聞き、理解することが大切です。
互いの思いを受け止めた上で、最終的には二人の判断で決めていくことが重要です。
後悔のない結婚式のために
結婚式は一生の思い出になるイベントです。
だからこそ、収支だけで判断するのではなく、「自分たちらしさ」を大切にしてほしいと思います。
私の場合、予算内で最大限「自分たちらしい結婚式」を目指しました。
衣装や映像など思い出に残るものにはお金をかけ、あまり重視していない部分は思い切って簡素化。
そのおかげで、費用も抑えつつ、満足のいく結婚式になりました。
大切なのは、何を優先するかを二人でしっかり話し合い、明確にすること。
そして、その選択に責任を持ち、後から「あれは間違いだった」と言わないこと。
結婚式の準備段階から二人で協力して乗り越えていく過程そのものが、結婚生活の第一歩になるのです。
黒字か赤字かという二択ではなく、「自分たちにとって最適な結婚式」を考えることが、本当の意味での成功につながるのではないでしょうか。
結婚式を黒字にするのはおかしい?のまとめ
結婚式を黒字にすることに対して、様々な視点から考えてきました。
「おかしい」と感じる理由には、結婚式の本来の意義との乖離や、ゲストへの配慮不足、文化的な価値観との衝突などがあります。
実際、黒字化は簡単ではなく、達成できるのはカップル全体の2割以下とのデータもあります。
それでも工夫次第では可能性はあり、特に80~100名規模の披露宴でゲスト一人当たりの費用を3万円以下に抑えることが鍵に。
具体的な計画を立てる際には、予算設定、ゲスト戦略、費用削減策、そして契約交渉など、様々な側面から検討することが大切ですね。
最終的には、結婚式を黒字にするか赤字を受け入れるかは、カップル自身の価値観次第。
- 「結婚式を黒字にするのはおかしい」という感覚を理解する
- 現実的な黒字化の可能性と条件を把握する
- 具体的な計画と工夫を知る
- 自分たちの価値観に合った選択をする
大切なのは、費用だけにとらわれず、二人にとって思い出に残る素敵な結婚式にすることです。
収支のことだけを考えて、大切な人たちへの感謝や二人の幸せな出発という本来の目的を見失わないようにしましょう。
結婚式を黒字にすることが「おかしい」かどうかは、結局のところ価値観の問題です。
正解はありません。
あなたとパートナーが納得できる形で、心からの祝福に包まれた結婚式になることを願っています。




















コメント