結婚式に夫婦で呼ぶと損をするのかな?って悩んでいませんか?
私も結婚式を挙げたときに「このゲストは夫婦で呼ぶべき?片方だけでもOK?」ってすごく迷いました。
結婚式の準備って、ゲストリストを作るだけでも一苦労。
特に「夫婦で呼ぶべきか」という問題は、費用面と人間関係の両方に関わるデリケートな問題なんですよね。
結論だけ先に言っちゃうと…
- 夫婦で呼ぶとご祝儀は5万円が相場(3万円×2ではない)
- 夫婦招待で増える費用は1組あたり約3〜5万円
- 日常的な交流がある夫婦は両方呼ぶのがベター
- 「少人数婚」という理由なら片方だけ招待でも失礼にならない
それでは、実体験と先輩花嫁さんたちの知恵をもとに、この悩みを徹底解説していきますね。
結婚式に夫婦で呼ぶと損をする?ぶっちゃけ、ご祝儀はいくらもらえる?

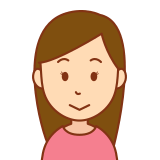
夫婦で呼んだらその分ご祝儀も多くもらえるよね?
そう思いますよね。でも実は、単純に「一人3万円×2人=6万円」とはならないんです。
- 夫婦連名での基本相場は5万円
- 関係性による金額の違い
- 地域による差も大きい
- 「損得」の本当の考え方
夫婦でのご祝儀相場と実際のバランスについて、私の経験も交えながらお話ししていきますね。
夫婦連名での基本相場は5万円
結婚式のご祝儀、夫婦連名の場合はいくらが相場なのでしょうか?
友人や同僚が単身で参加する場合の相場が3万円だとすると、「3万円×2=6万円」になりそうなものですが、実際はそうではありません。
夫婦で招待した場合の一般的な相場は5万円なんです。
これは私の結婚式でも同じでした。
友人夫婦からは基本的に5万円のご祝儀をいただくことが多かったです。
つまり、単純計算では「6万円-5万円=1万円」の差額が生じることになります。
この1万円の差があるため、単純に「人数×単価」で計算すると、夫婦で呼ぶと少し「損」に感じてしまうかもしれません。
でも、それは本当に「損」なのでしょうか?
関係性による金額の違い
ご祝儀の金額は、実は新郎新婦との関係性によって大きく変わってきます。
例えば、新郎新婦より年上の方や親族の場合は、8〜10万円が一般的です。
私の結婚式では、親戚の夫婦からは10万円をいただいたケースもありました。
一方で、同年代の友人夫婦からは5万円というパターンが多かったです。
これは「年長者からは多めに包む」という日本の文化的背景があるからなんですね。
つまり、誰を招待するかによって、予想されるご祝儀の金額は変わってくるということ。
単純に「夫婦だから損」とは言えない側面があるのです。
地域による差も大きい
意外と見落としがちなのが、地域による違いです。
例えば北海道では、結婚式を会費制で行うことが多く、ご祝儀の金額自体が低めに設定されていることが一般的です。
私の友人は北海道出身で、彼女の結婚式では夫婦で3万円という相場でした。
一方、関西や関東では5万円が一般的です。
東北や九州などでも地域ごとに微妙に相場が異なります。
こうした地域差を考慮せずに一律に「損得」を計算するのは難しいのが現実です。
「損得」の本当の考え方
結婚式の費用対効果を考える際、単純な「損得」だけで考えるのはあまり意味がないかもしれません。
実は結婚式の総費用の6〜7割をご祝儀で賄うカップルが多いんです。
全国平均のご祝儀総額は約228万円と言われています。
ゲスト1人あたりの平均負担額は約3.3万円で、50人招待で約165万円が目安になります。
また、内祝いの相場はご祝儀の1/2〜1/3程度のため、高額なご祝儀をいただいても、その分返礼品の費用も増えるという側面もあります。
こうした全体のバランスを見ると、夫婦で招待することの「損得」は、単純なご祝儀の金額だけでは測れないものがあるんですね。
大切な人たちと特別な日を共有できる喜び。
それこそが結婚式の本当の価値なのかもしれません。
結婚式に夫婦で呼ぶと増える費用(料理や引き出物等)

結婚式に夫婦で招待すると、どれくらい費用が増えるのか気になりますよね。
私も結婚式を計画していたとき、「この人は夫婦で呼ぶべき?でも予算オーバーになるかも…」と悩みました。
実際にどんな費用が増えるのか、具体的な数字と共に解説していきますね。
- 料理・飲み物代は人数分増える
- 引き出物費用の増加
- その他の人数比例費用
- 総額でどれくらい増えるのか
料理・飲み物代は人数分増える
結婚式で最も大きく費用が増えるのは、やはり料理と飲み物代です。
これらは完全に人数比例で増えていきます。
具体的な相場を表にまとめてみました。
| 項目 | 1人あたりの相場 | 夫婦2人分 |
|---|---|---|
| 料理代 | 約16,000円 | 約32,000円 |
| 飲み物代 | 約4,400円 | 約8,800円 |
| 合計 | 約20,400円 | 約40,800円 |
この表を見ると、料理と飲み物だけで夫婦1組を招待すると約4万円の費用増になることがわかります。
私の結婚式では、ホテルでの開催だったため料理代がさらに高く、1人あたり約2万円でした。
夫婦で呼ぶと4万円。
この金額は決して小さくありません。
10組の夫婦を招待すると、それだけで40万円の費用増です。
予算との兼ね合いをよく考える必要があります。
引き出物費用の増加
料理代に次いで大きいのが引き出物の費用です。
引き出物も基本的に人数分必要になるため、夫婦で招待すれば2人分の費用がかかります。
具体的な金額を表にまとめました。
| 引き出物のグレード | 1人あたりの相場 | 夫婦2人分 |
|---|---|---|
| スタンダード | 約5,000円 | 約10,000円 |
| 平均的な相場 | 約6,900円 | 約13,800円 |
| 高級タイプ | 約10,000円 | 約20,000円 |
私の結婚式では、引き出物は1人あたり7,000円程度のものを用意しました。
夫婦で呼んだ場合は1組あたり14,000円の費用です。
ここでコストを抑えるテクニックとして、夫婦には共有できる1つの高級引き出物にするという方法もあります。
例えば、1人用なら5,000円のものを、夫婦には8,000円の共有できるアイテム1つにするという方法です。
これで若干のコスト削減になりますが、それでも人数が増えれば費用は比例して増加します。
その他の人数比例費用
料理代と引き出物以外にも、人数に比例して増える費用があります。
| 項目 | 1人あたりの相場 | 夫婦2人分 |
|---|---|---|
| 席次表・席札 | 約300円 | 約600円 |
| プログラム | 約200円 | 約400円 |
| テーブル装花 | 約1,000円 | 約2,000円 |
| サービス料 | 約2,000円 | 約4,000円 |
これらは1人あたりの金額は小さいですが、積み重なると結構な金額になります。
特にサービス料は会場によって10〜15%程度かかることが多く、料理代などに比例して増えるため、侮れない費用です。
私の結婚式では、こうした細かい費用が予想以上に膨らんで、予算オーバーになりそうになりました。
事前にしっかり計算しておくことをおすすめします。
総額でどれくらい増えるのか
では、夫婦1組を招待することでどれくらい費用が増えるのでしょうか。
全てを合計すると、以下のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 料理・飲み物代 | 約40,800円 |
| 引き出物 | 約13,800円 |
| その他細かい費用 | 約7,000円 |
| 合計 | 約61,600円 |
この金額から夫婦からもらえるご祝儀相場の5万円を引くと、約11,600円の赤字になります。
つまり、単純計算では夫婦1組を招待するたびに約1万円強の「損」をしていることになります。
これが「結婚式に夫婦で呼ぶと損をする」と言われる理由です。
ただし、これはあくまで平均的な数字。
親族などからは高額なご祝儀をもらえることも多いですし、何より大切な人と特別な日を共有できる価値は金額には換算できません。
それぞれの状況と優先順位を考えて、バランスの取れた判断をすることが大切です。
結婚式に夫婦で呼ばないと失礼?どうするか判断基準

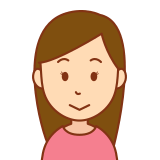
この友人は夫婦で呼ぶべき?でも配偶者とはあまり親しくないし…
このように悩んだ経験はありませんか?
私も結婚式の準備中に、この問題で頭を悩ませました。
結局のところ、夫婦で呼ばないことが失礼にあたるかどうかは、関係性や状況によって大きく異なります。
判断基準となるポイントを詳しく解説していきますね。
- 日常的な交流の有無で判断
- グループ内の統一性も重要
- 過去の招待履歴を考慮する
- 親族と友人では基準が異なる
日常的な交流の有無で判断
最も重要な判断基準は、配偶者との日常的な交流があるかどうかです。
以下の表は、交流の頻度による招待の判断基準の目安です。
| 交流の頻度 | 招待すべきか | 配慮すべきポイント |
|---|---|---|
| 頻繁に会う(月1回以上) | 夫婦で招待が望ましい | 招待状も連名で出すと良い |
| たまに会う(年数回程度) | 夫婦で招待するのが無難 | 招待状は個人名でも可 |
| ほとんど会わない(数年に一度) | 片方のみの招待でも問題なし | 事前に理由を伝えると良い |
| 一度も会ったことがない | 片方のみの招待が一般的 | 招待後の会食などで紹介する配慮を |
私の場合は、大学時代の友人を招待する際、そのパートナーと一度も会ったことがなかったため、友人のみを招待しました。
事前に「少人数での結婚式なので…」と伝えたところ、むしろ「配慮してくれてありがとう」と言われたんです。
こういった事例からも、日常的な交流の有無は重要な判断基準と言えます。
グループ内の統一性も重要
友人グループ内での扱いに差をつけると、人間関係にヒビが入る可能性もあります。
例えば、同じサークルの友人5人のうち、3人は夫婦で招待して2人は本人のみ…というと「なぜ?」という疑問や不満が生じるかもしれません。
こうした状況を避けるため、グループ内では統一した基準で招待することが望ましいです。
| グループの種類 | 推奨される招待方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 学生時代の友人グループ | 全員同じ基準で招待 | 全員夫婦か全員本人のみで統一 |
| 職場の同僚グループ | 役職や親密度で統一 | 上司は夫婦、同僚は本人のみなど |
| 趣味のサークルなど | 親密度で統一 | 頻繁に会う人は夫婦、そうでない人は本人のみ |
私の結婚式では、大学の友人グループ全員を「本人のみ」で招待し、職場の同僚も全員「本人のみ」で統一しました。
その代わり、結婚式後に別途、パートナーも交えた食事会を開いて交流する機会を設けました。
こうすることで、結婚式当日の費用を抑えつつ、人間関係も大切にすることができました。
過去の招待履歴を考慮する
過去に相手の結婚式に招待された場合は、お返しとして同等の扱いをするのがマナーとされています。
例えば、友人の結婚式に夫婦で招待されたのに、自分の結婚式では本人だけを招待するのは、少し気まずい状況になるかもしれません。
| 過去の招待パターン | あなたの招待方法 | 説明 |
|---|---|---|
| 夫婦で招待された | 夫婦で招待するのが望ましい | 同等の待遇を返すことがマナー |
| 本人のみ招待された | 本人のみでも問題なし | 相手も同様の判断をしていた |
| 二次会のみ招待された | 同様に二次会招待で可 | 同等の扱いが基本 |
私の友人は、「過去に招待してもらった相手には同等以上の待遇で返す」というルールを自分で決めていました。
これは一つの賢い判断基準だと思います。
親族と友人では基準が異なる
親族と友人では、招待の基準が異なることも知っておくべきポイントです。
親族の場合は「両親との関係性」が優先されるため、新郎新婦と直接の交流がなくても招待するケースが多いです。
| 関係性 | 一般的な招待パターン | 理由 |
|---|---|---|
| 親族(叔父叔母など) | 基本的に夫婦で招待 | 家族単位での付き合いが基本 |
| 親の友人・知人 | 状況に応じて夫婦または代表者 | 親との関係性を尊重 |
| 自分の友人 | 親密度に応じて判断 | 個人的な関係性が基準 |
| 仕事関係 | 上司は夫婦、同僚は個人的に判断 | 役職や関係性に応じて対応 |
私の結婚式では、叔父叔母は全て夫婦で招待しましたが、従兄弟は個人的な交流頻度で判断しました。
親族内でも細かい線引きをすることで、予算内でバランスの取れた招待ができました。
結局のところ、「夫婦で呼ばないと失礼」とは一概に言えません。
大切なのは、新郎新婦とゲスト双方の関係性や経済状況を考慮し、一貫性のある判断をすることです。
迷った場合は「自分がその立場ならどうしてほしいか」という視点で考えると良いでしょう。
結婚式に夫婦の片方だけ呼ぶ場合の角が立たない伝え方
予算や会場の都合で夫婦の片方だけを招待せざるを得ない場合、どう伝えれば角が立たないのでしょうか?
私も結婚式の準備中に、この悩みで夜も眠れないことがありました。
どうすれば相手を傷つけず、スムーズに理解してもらえるのか。
実体験をもとに、効果的な伝え方をご紹介します。
- 基本方針をはっきり伝える
- 個別事情への配慮を示す
- 招待状作成時の工夫
- 返信時のフォローアップ
基本方針をはっきり伝える
夫婦の片方だけを招待する場合、まずは結婚式の基本方針を明確に伝えることが大切です。
「親族と親しい友人中心の少人数式」という理由なら、多くの人は理解してくれるでしょう。
私の結婚式では、「両親に近くで見守ってほしいため、最小限の人数で行う」と伝えました。
これは角が立ちにくい理由の一つです。
具体的な伝え方としては、例えば次のようなメッセージが効果的です。
こうした前置きをすることで、相手も「特別扱いされている」と感じることができ、配慮も伝わります。
私の経験では、このように伝えた友人からは「そういう方針なら理解できる」と言ってもらえました。
正直でシンプルな理由は、相手の心に響きます。
個別事情への配慮を示す
次に重要なのは、個別の事情への配慮を示すことです。
親密さの違いを丁寧に説明したり、遠方からの移動の負担を考慮していることを伝えたりするのが効果的です。
例えば、私は大学時代からの親友には次のように伝えました。
また、遠方に住む友人には
このように、相手の立場に立った配慮を示すことで、「あなたのことを考えている」というメッセージが伝わります。
私の結婚式では、このアプローチで多くの友人に理解してもらえました。
大切なのは、相手を選別しているのではなく、状況に応じた最善の選択をしていることを伝えること。
誠実さが何よりも重要です。
招待状作成時の工夫
招待状を作成する際にも、配慮が必要です。
宛名は個人名のみ記載して、メッセージ欄に「ご都合がつかない場合は遠慮なくお知らせください」との一文を添えると良いでしょう。
私は招待状の宛名は個人名のみにして、中の文面で以下のように書きました。
また、二次会がある場合は、配偶者も含めて二次会に招待するという方法もあります。
こうすることで、「排除している」という印象を和らげることができます。
私の結婚式では、一部の友人は本人のみ披露宴に招待し、配偶者は二次会から参加してもらうというスタイルにしました。
これは予算内でより多くの人と時間を共有するための良い妥協点となりました。
返信時のフォローアップ
招待状の返信があった際のフォローも大切です。
特に、欠席する配偶者への配慮の言葉を添えると良いでしょう。
私は返信をもらった友人には必ず電話をして、直接感謝の言葉を伝えるようにしました。
この一手間が、関係性を深めることにつながりました。
また、結婚式後に本当に夫婦で会う機会を設けることも忘れないようにしましょう。
約束したことは必ず実行することで、誠実さが伝わります。
私は結婚式の3か月後に、招待できなかった配偶者も含めた食事会を開きました。
これがかえって関係性を深める良い機会となり、「結果オーライ」だったと感じています。
このように、夫婦の片方だけを招待する場合は、伝え方に工夫をすることで、角が立つことなくスムーズに理解してもらえる可能性が高まります。
大切なのは、「費用削減のため」などの直接的な表現を避け、関係性の深さや式のコンセプトを軸にした誠実な説明を心がけることです。
一方的な通知ではなく、できれば事前に口頭で意向を伝える機会を設けるのが理想的ですね。
私の経験からも、丁寧なコミュニケーションが人間関係を守るカギであると実感しています。
「結婚式に夫婦で呼ぶと損?」のまとめ
結婚式に夫婦で呼ぶと本当に「損」なのか、様々な角度から検討してきました。
数字だけを見れば確かに「損」に見えるかもしれませんが、人間関係や結婚式の本質を考えると、単純に損得では語れないものがありますね。
ここで、もう一度おさらいしておきましょう。
- 夫婦のご祝儀相場は5万円(3万円×2ではない)
- 夫婦1組を招待すると約3〜5万円の費用増
- 日常的に交流がある夫婦は両方招待するのがベター
- 招待できない場合は「少人数婚」という理由が角が立ちにくい
結婚式に夫婦で呼ぶと損をするかどうかは、単純なお金の計算だけでは決められません。
大切な人たちと特別な日を過ごせるという価値は、金額に換算できないものがあります。
それでも予算は現実的な問題。
限られた予算の中で、最高の結婚式を実現するためには、ゲストリストの検討は避けて通れません。
私も何度も書き直しましたが、最終的には「この人と絶対に共有したい」という思いを優先しました。
結局のところ、一番大切なのは新郎新婦の気持ち。
自分たちが心から満足できる選択をすることが、結婚式を成功させる秘訣なのかもしれません。
みなさんも、周りの意見に振り回されず、自分たちらしい結婚式を実現してくださいね。
そして、もし夫婦の片方だけを招待するという選択をした場合は、丁寧な言葉選びとフォローアップを忘れずに。
結婚式は終わっても、人間関係は続いていくのですから。




















コメント