いとこの結婚式のご祝儀で家族で出席する際の相場について、経験者として詳しくお伝えします。
結婚式のご祝儀って、特に家族連れの場合はいくら包めばいいのか迷いますよね。
私もいとこの結婚式に家族で参列したとき、「子供も含めていくら包むべきか」「他の親族とバランスは取れるのか」と悩んだ経験があります。
結論からお伝えすると…
- 家族3人(夫婦+子ども1人)の場合→7万円が基本ライン
- 家族4人(夫婦+子ども2人)の場合→7~8万円が標準的
- 家族5人(夫婦+子ども3人)の場合→8~10万円が一般的
- 子どもの年齢によって加算額は変わる(0~2歳は基本加算不要)
- 親族内のバランスを事前に確認するのが最重要
それでは、これらのポイントについて詳しく解説していきますね。
いとこの結婚式のご祝儀は?家族3人・家族4人・家族5人で出席する際の相場(子供が何歳なら加算する?)

いとこの結婚式に家族で参列するとき、いちばん頭を悩ませるのがご祝儀の金額問題。人数が増えれば増えるほど、「適切な金額」の判断が難しくなりますよね。
私自身、子どもを連れていとこの結婚式に出席したとき、正直「子どもの分はいくら加算すればいいの?」と迷いました。
まず基本的な考え方として、いとこへのご祝儀相場は大人1人なら3~5万円が標準です。でも家族で参列するときは、子どもの年齢や人数に応じて金額を調整していく必要があります。
特に重要なのは、子どもにも「席料」や「食事代」がかかっているという点。
子どもの年齢による加算の考え方
子どもの年齢によって、結婚式での扱いが大きく変わります。これがご祝儀額にも直結するポイント。
- 乳幼児(0~2歳):基本的に加算不要
- 未就学児(3~6歳):5千円~1万円の加算
- 小学生(7~12歳):1万円~1万5千円の加算
- 中学生以上(13歳~):大人と同等(1万5千円~2万円程度)の加算
なぜこのような区分けになるのでしょうか?結婚式での扱いを考えると分かりやすいです。
0~2歳の赤ちゃんは通常、親の膝の上で過ごすことが多く、専用の席や食事が用意されないケースがほとんど。そのため、ご祝儀の加算は基本的に不要とされています。
一方、3歳以上になると子ども用の椅子や食事(お子様プレート)が用意されることが一般的です。このあたりから費用が発生するため、加算が必要になってきます。
さらに小学生になると食事内容も充実し、中学生以上になるとほぼ大人と同等の扱いになるため、それに応じて加算額も増えていくのです。
家族人数別のご祝儀相場
それでは具体的に、家族の人数構成別にご祝儀相場をご紹介します。
| 家族構成 | 子どもの年齢 | ご祝儀相場 | 実際に包む金額例 |
|---|---|---|---|
| 家族3人 (夫婦+子1人) |
0~2歳 | 5万円程度 | 5万円 |
| 3~6歳 | 5万5千円~6万円 | 5万円または7万円 | |
| 7~12歳 | 6万円~6万5千円 | 7万円 | |
| 13歳以上 | 7万円~8万円 | 7万円または8万円 | |
| 家族4人 (夫婦+子2人) |
いずれも0~2歳 | 5万円程度 | 5万円 |
| いずれも3~6歳 | 6万円~7万円 | 7万円または8万円 | |
| いずれも7~12歳 | 7万円~8万円 | 7万円または8万円 | |
| いずれも13歳以上 | 9万円~11万円 | 10万円 | |
| 家族5人 (夫婦+子3人) |
いずれも0~2歳 | 5万円程度 | 5万円 |
| いずれも3~6歳 | 6万5千円~8万円 | 7万円または8万円 | |
| いずれも7~12歳 | 8万円~9万5千円 | 8万円または10万円 | |
| いずれも13歳以上 | 11万円~14万円 | 11万円~14万円 |
実際に包む金額は、「4」(死を連想)や「9」(苦を連想)などの縁起の悪い数字を避け、「5」(ご縁)や「8」(末広がり)などの縁起の良い数字を選ぶのが一般的です。
例えば、計算上は「6万円」が相場でも、実際には「5万円」か「7万円」を選ぶといった調整をします。
子どもの年齢が混在する場合の考え方
実際には、「子ども全員が同じ年齢層」ということは少なく、年齢がバラバラのケースが多いですよね。
そんなときは、それぞれの子どもの年齢に応じた加算額を合計して、最終的に縁起の良い金額に調整するのがおすすめです。
例えば、夫婦に0歳の赤ちゃんと5歳の子どもがいる場合
→実際には「5万円」か「7万円」を選ぶことになります。
子どもの年齢や人数によって相場は変わりますが、大切なのは無理のない範囲でお祝いの気持ちを伝えること。地域や親族間の習慣も考慮しながら、適切な金額を決めていきましょう。
いとこの結婚式に家族で出席する場合、ご祝儀は「まとめて」or「個別」?

いとこの結婚式に家族で参列する場合、「ご祝儀は家族全員分をまとめて渡すべきか、それとも個別に包むべきか」という疑問が生じることがあります。
私自身、初めていとこの結婚式に夫と子どもを連れて出席したとき、この点で迷った記憶があります。周りの人に聞いても「うちはまとめてだよ」「いや、別々じゃない?」と意見が分かれて、さらに混乱したものです。
結論から言うと、小さなお子さんを含む家族で招待された場合は、「まとめて包む」のが一般的かつ自然な選択です。それには、いくつかの理由があります。
家族でまとめて包むのが基本の理由
家族単位でご祝儀をまとめる理由はいくつかあります。
- 招待状の宛名が「〇〇家御一同様」など家族単位になっている
- 結婚式での席や引き出物も家族単位で用意されることが多い
- 小さな子どもは独立した収入がない
- 親族間の付き合いは「家と家」の関係という側面がある
特に重要なのは招待状の宛名です。「〇〇家御一同様」のように、家族全体を一つの単位として招待されている場合は、ご祝儀も家族でまとめて包むのが自然です。
また結婚式では、席次表も「〇〇家」として一つのテーブルにまとめられることが多く、引き出物も家族単位で用意されます。そのため、お返しの意味合いも持つご祝儀も、同じく家族単位で考えるのが筋道としては通っています。
何より、小さなお子さんは独立した収入がないため、親が子どもの分も包むのが当然という考え方があります。親族間の付き合いも「家と家」という側面が強いため、家族単位でまとめるのが自然なのです。
ご祝儀袋の記名方法
家族でまとめて包む場合、ご祝儀袋の表書きや中袋への記名方法も気になるところですよね。
私が初めて家族でいとこの結婚式に出席したとき、「子どもの名前はどこに書くの?」と悩みました。調べてみると、以下のような方法が一般的とされています。
- 表書き:夫婦の連名または「〇〇家一同」と記載
- 中袋の裏面:住所・電話番号と共に、出席する全員の名前を記載
例えば、表書きに「山田太郎・花子」と夫婦の名前を書き、中袋の裏に「山田太郎、花子、長男健太、長女さくら」のように家族全員の名前を記載します。あるいは、表書きに「山田家一同」と書いて、中袋に詳細を記すという方法もあります。
これは単なる形式ではなく、「誰からいくら頂いたか」を新郎新婦側が把握するための重要な情報です。後々のお返しの際にも、この情報をもとに判断されるため、しっかりと記載しておきましょう。
個別に包むべきケース
一方で、以下のようなケースでは、個別にご祝儀を包むのが適切な場合もあります。
- 招待状が個人宛てに別々に届いている
- 成人した子どもが親と同居しているが、経済的に独立している
- 親族内で「成人した者は個別に包む」という慣習がある
特に、すでに社会人として働いている成人した子どもが親と同居している場合、その子どもは経済的に独立しているとみなされ、別にご祝儀を包むことが期待されるケースがあります。
また、招待状が「〇〇様」と個人宛てに別々に届いている場合も、個別に包むことを想定されているシグナルかもしれません。
親族内の慣習も重要な判断材料です。「うちの親族では、成人した者は皆個別に包む」というような暗黙のルールがある場合は、それに従うのが無難でしょう。
迷った場合は、親や親族に相談するのが最も確実です。
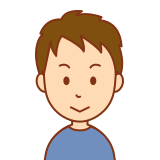
いとこの結婚式のご祝儀、うちはどうするの?
と率直に尋ねてみれば、家族や親族の慣習に沿った適切な判断ができるでしょう。
いずれにせよ、小さなお子さんを含む一般的な家族構成であれば、「まとめて包む」のが基本と考えて間違いありません。
いとこの結婚式のご祝儀の「親族内バランス」の取り方

いとこの結婚式のご祝儀で意外と見落としがちなのが「親族内バランス」という視点です。
私自身、いとこの結婚式に出席したとき、後になって「あれ?うちだけ少なかったのかな」と不安になったことがあります。逆に「みんなより多く包んでしまって、相手に迷惑をかけたかも」と心配になったこともありました。
親族内でのご祝儀のバランスは、単に「見栄」の問題ではなく、その後の親族付き合いにも関わる重要な要素です。では、どうすれば適切なバランスを取れるのでしょうか?
親族内バランスが重要な理由
まず、なぜ親族内でのご祝儀のバランスが重要なのかを考えてみましょう。
- 親族間の「家と家」の付き合いの一側面である
- 著しい差があると、気まずさやしこりが残る可能性がある
- 新郎新婦側も「半返し」などの判断に困る
- 長期的な親族関係の潤滑油になる
ご祝儀は単なる「お金」ではなく、親族間の関係性を表す象徴的な意味合いも持っています。特に日本の文化では、こうした「形式」が関係性を円滑にする役割を果たしています。
例えば、同じ立場(例:いとこ同士)なのに、AさんとBさんのご祝儀額に大きな差があると、「Aさんは親戚付き合いを大切にしている」「Bさんは親戚に冷たい」といった誤解や摩擦が生じる可能性があります。
また、ご祝儀を受け取る新郎新婦側も、「半返し」(ご祝儀の半額程度の引き出物を用意する習慣)の判断に困ることがあります。親族内で金額に大きな差があると、引き出物を統一するか個別に対応するかで悩むことになるのです。
親族内での適切なバランスを取ることは、その後の長期的な親族関係をスムーズに保つための潤滑油となります。
親族内バランスを取るための具体的な方法
では、親族内でのバランスを取るためには、具体的にどうすればよいのでしょうか?
- 親(結婚するいとこの叔父・叔母)に相談する
- 兄弟姉妹やいとこ(同世代)と相談する
- 過去の親族の結婚式の例を思い出す
最も確実な方法は、自分の親(結婚するいとこの叔父・叔母にあたる人)に相談することです。親世代は親族間の関係性や慣習をよく理解しており、「うちの兄弟(いとこの親)とは〇万円くらいにしようと話している」といった具体的な情報を教えてくれることが多いです。
また、兄弟姉妹やいとこなど、同世代の親族と相談するのも有効です。特に結婚式に出席する兄弟がいる場合は、金額を合わせるのがスムーズでしょう。同じ立場のいとこが他にいれば、「いくら包む予定?」と何気なく聞いてみるのもありです。
過去の親族の結婚式の例も参考になります。以前、同じような立場で他のいとこの結婚式に出席したことがあれば、その時の金額を思い出してみましょう。もちろん、物価変動や自身の状況変化も考慮する必要がありますが、ベースラインとしては役立ちます。
立場や状況に応じた調整
親族内のバランスを基本としつつも、自分の立場や状況に応じた調整も必要です。
- いとことの親密度による調整
- 自分の経済状況に応じた現実的な判断
- 家族構成に合わせた加算
- 地域の慣習を考慮
まず考慮すべきは、いとことの親密度です。普段から頻繁に連絡を取り合う親しい間柄なら、相場より少し多めに包むことで特別な関係性を表現することもあります。逆に、ほとんど付き合いがない場合は、相場の下限を参考にしても問題ないでしょう。
次に、自分の経済状況も重要な要素です。親族内の相場が高くても、自分の経済状況を無視して無理に合わせる必要はありません。むしろ、自分の状況に応じた金額に、心のこもったメッセージカードを添えるなどの工夫をする方が誠実です。
家族構成による加算も忘れてはいけません。先ほど説明したように、お子さんの年齢や人数に応じた加算を行いましょう。例えば、親族内の夫婦の相場が5万円なら、そこに子どもの分を適切に加算して調整します。
最後に、地域の慣習も無視できません。東京と地方では相場が異なることも多く、特に地方では「いとこへは〇万円」という明確な目安があることもあります。
これらの要素を総合的に考慮し、親族内のバランスを保ちつつも、自分なりのお祝いの気持ちを形にすることが大切です。
いとこの結婚式のご祝儀は?家族で出席する際の相場のまとめ
いとこの結婚式のご祝儀について、家族で出席する際の相場や考え方をお伝えしてきました。最後に、重要なポイントをおさらいしておきましょう。
結婚式のご祝儀は単なる「お金」ではなく、お祝いの気持ちと共に、親族間の関係性を築く大切な要素です。特に子連れで参列する場合は、さまざまな要素を考慮してバランスの取れた金額を決めることが重要です。
ここまでお伝えした内容をまとめると、以下のポイントがいとこの結婚式のご祝儀を決める際の重要な指針となります。
- 家族3人(夫婦+子ども1人)の場合は5~7万円が基本
- 家族4人(夫婦+子ども2人)の場合は7~8万円が標準的
- 家族5人(夫婦+子ども3人)の場合は8~10万円が一般的
- 3歳以上の子どもは年齢に応じて加算が必要
- 家族でまとめて包むのが基本(子どもが小さい場合)
- 親族内のバランスは親や親族に相談して把握するのがベスト
最終的に大切なのは、無理のない範囲でお祝いの気持ちを形にすること。相場はあくまで目安であり、自分の状況や親族との関係性、地域の慣習などを考慮して、心からのお祝いの気持ちを込めたご祝儀を包みましょう。
また、ご祝儀以外にも、結婚式当日の子どもの服装や振る舞いについても事前に考えておくと安心です。小さなお子さんがいる場合は、式中に泣いたり騒いだりしたときの対応も考えておくとよいでしょう。
いとこの結婚式は、親族が集まる貴重な機会です。ご祝儀の金額に悩むのは当然ですが、それ以上に大切なのは、心からお祝いする気持ちと親族との絆を深めること。この記事が、いとこの結婚式に家族で参列される方の参考になれば幸いです。




















コメント