結婚式で元が取れる人数について、気になっていませんか?私も結婚式を挙げたとき、「招待人数はどのくらいが良いのかな」「費用って本当に回収できるの?」と悩んだ経験があります。
多くの人が「結婚式は一生に一度の大切な日」と考える一方で、「費用対効果も考えたい」と思うのは自然なこと。
今回は私の実体験と先輩花嫁さんたちの知恵をもとに、結婚式の招待人数と費用回収について徹底解説します。
- 元が取れる最適な招待人数の目安
- 費用を抑えながら満足度の高い結婚式を叶える方法
- 「元を取る」にこだわりすぎるリスク
- みんなが実際に選んでいる招待人数とその決め手
この記事を読めば、あなたにぴったりの招待人数が見えてくるはず。
さあ、理想の結婚式に向けて、一緒に考えていきましょう!
結婚式で元取れる人数をシミュレーション

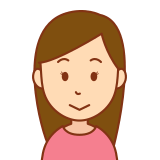
結婚式で元を取れる人数って実際どのくらい?
という疑問、持ったことありませんか?私も結婚準備中にこの問題で頭を悩ませました。
実は、元が取れる人数は結婚式のスタイルや予算によって大きく変わってくるんです。
招待する人数によって費用が変わる部分と変わらない部分があり、そのバランスが重要なポイント。
まずは、結婚式のスタイル別に見た「元が取れる人数」の傾向を見ていきましょう。
- 少人数婚(10人以下または30人程度)
- 一般的な規模(約60人)
- 大規模(80人以上)
それぞれのスタイルでどのくらいの費用がかかり、どのくらいのご祝儀が期待できるのか、詳しく見ていきましょうね。
少人数婚の場合
少人数婚は「家族婚」(10人以下)と「親族中心の少人数婚」(30人程度)に分けられます。
このスタイルを選ぶと、演出やお色直しをシンプルにすることで、自己負担ゼロや黒字にすることも十分可能です。
特に家族婚では、両親や祖父母からの高額なご祝儀が期待できるため、費用を抑えやすい傾向にあります。
私の友人Aさんは、両家の両親と兄弟だけの8人で挙式をして、費用80万円に対してご祝儀100万円で、20万円のプラスになったんですよ!
少人数だからこそ、一人一人と深く交流できる時間も確保できるのがいいところ。
一般的な規模の場合
日本の結婚式の平均的な人数は60人前後と言われています。
この規模になると、費用の相場は約315万円、ゲスト一人当たりのご祝儀平均額が3.3万円だとすると、自己負担は少し出るケースが多いですね。
でも工夫次第で、この自己負担を抑えることは可能です。
友人Bさんは、60人の結婚式を挙げて、費用300万円に対してご祝儀が280万円。
20万円の自己負担で済んだのは、曜日や時間帯の選び方などを工夫したからだそうです。
大規模パーティーの場合
80人以上、特に80~100人程度の大規模な結婚式では、黒字になる可能性が高くなります。
これは、ゲストが多いほどご祝儀総額が増える一方で、会場費や演出費などの固定費は人数が増えても大きく変わらないため。
結果として1人あたりのコストが下がり、「元」が取りやすくなるんです。
例えば、100人規模の場合、ご祝儀総額の相場は約340万円(1人あたり3.4万円)となり、費用を抑えれば黒字化も十分可能です。
| 招待人数 | 平均費用 | 想定ご祝儀 | 収支バランス | 元が取れる可能性 |
|---|---|---|---|---|
| 10人以下(家族婚) | 80~100万円 | 100~120万円 | +20万円前後 | 高い |
| 30人程度(少人数婚) | 150~200万円 | 150~180万円 | ±0~-20万円 | 工夫次第で可能 |
| 60人前後(一般的規模) | 300~350万円 | 280~310万円 | -20~-40万円 | やや難しい |
| 80人以上(大規模) | 400~450万円 | 380~440万円 | -20~±0万円 | 高い |
| 100人以上 | 450~550万円 | 500~600万円 | +50万円前後 | 非常に高い |
もちろん、これはあくまで平均的な目安です。
ご祝儀の平均額はゲストの属性によって大きく変わることも忘れてはいけません。
親族が多いと平均額が上がる傾向があるんですよ。
また、結婚式の内容や会場、時期によっても費用は変動します。
元が取れる人数の目安は10人以下の家族婚、30人程度の少人数婚、80人以上の大規模パーティーがおすすめです。
でも、「元を取る」ことだけでなく、結婚式の持つ意味や思い出も大切にしたいですね。
結婚式で「元を取る」ためにできる工夫

結婚式の費用を抑えながらも素敵な一日にするために、私も含め多くの先輩花嫁さんたちが実践してきた工夫があります。
「元を取る」というとなんだか打算的に聞こえるかもしれませんが、要は「賢く費用をコントロールして、後悔しない結婚式にする」ということ。
費用を抑えることで、新婚生活や将来の資金に余裕ができるというメリットもあるんですよ。
それでは、結婚式で「元を取る」ためにできる具体的な工夫を、いくつかのポイントに分けてご紹介します。
- 日取りや時間帯の選び方
- 会場・スタイルの選択方法
- アイテム別の節約術
- メリハリをつけた費用配分
どれも実際に試されて効果があった方法なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
日取りや時間帯の選び方
結婚式の日取りや時間帯を工夫するだけで、会場費が大幅に安くなることをご存知ですか?
私の結婚式は1月の仏滅の日に挙げましたが、同じ会場の人気日と比べて約15万円も安くなりました。
オフシーズン(夏・冬)や仏滅、平日、夕方などの「人気のない日取り」を選ぶと、会場側も予約を入れたいので、かなりお得な料金設定になっていることが多いんです。
例えば、同じ土曜日でも「大安」と「仏滅」では10~20万円の差がつくことも珍しくありません。
また、昼間の披露宴よりも、夕方からのナイトウェディングを選ぶと、料金が下がるケースが多いですよ。
「でも、ゲストが集まりにくくなるんじゃ…」と心配する方もいるかもしれませんが、本当に大切な人たちは日程を合わせてくれるものです。
むしろ、人数が絞られることで、より親密な式になるというメリットもあります。
会場・スタイルの選択方法
結婚式の会場やスタイルで費用は大きく変わります。
ホテルや専門式場より、レストランウェディングや1.5次会スタイルを選ぶと、一人当たりの費用を抑えられることが多いです。
私の友人Cさんは、都内のおしゃれなイタリアンレストランを貸切にして40人規模のウェディングを開催。
総額180万円と、同規模のホテル婚より100万円も安く済ませることができたそうです。
会費制パーティーや1.5次会のようなカジュアルなスタイルを選ぶと、ご祝儀ではなく定額の会費をいただくことになるので、収入と支出のバランスが取りやすくなります。
また、あらかじめ会場側が用意している「お得なプラン」を活用するのも賢い方法。
オフシーズン限定プランや記念日プラン、平日プランなどは、通常より10~30%オフになることも珍しくありません。
アイテム別の節約術
結婚式には様々なアイテムが必要ですが、すべてにこだわる必要はありません。
例えば、私は招待状をネットで購入して自分たちで印刷したことで、約5万円の節約になりました。
ペーパーアイテム(招待状、席次表など)は、オンライン招待状やWeb受付を活用すれば、大幅に費用を削減できます。
友人Dさんは、結婚式の案内をオンラインで行い、当日の受付もQRコードで済ませたところ、約8万円の節約になったそうです。
また、引出物やプチギフトは自分たちで手配したり、DIYしたりすることで、コストダウンが可能。
装花やケーキもシンプルなものを選ぶか、一部を造花や既製品で代用するという方法もあります。
ドレスや小物は、フリマアプリやお譲りサービスを活用すれば、新品の半額以下で調達できることも。
「中古」と聞くと抵抗がある方もいるかもしれませんが、結婚式で使うドレスは着る時間が短いこともあり、状態の良いものが多いんですよ。
メリハリをつけた費用配分
すべてを節約するのではなく、メリハリをつけて費用配分することも大切です。
私は料理とカメラマンにはしっかり予算をかけ、その他の部分で節約しました。
料理やドリンクなど、ゲストの満足度に直結する部分には予算をかけ、他の部分で節約する「一点豪華主義」は効果的です。
例えば、友人Eさんは料理にこだわり、有名シェフのコースを提供したものの、装花はシンプルに、ムービーは自作するなど工夫。
ゲストからは「料理が素晴らしかった」と大好評だったそうです。
オリジナル演出や地元食材を使った料理など、費用を抑えつつもゲストに喜ばれる工夫を取り入れるのも良いですね。
思い出に残るのは、必ずしも「高価なもの」ではなく、「心のこもったおもてなし」だということを忘れないでくださいね。
結婚式で「元を取る」ことにこだわりすぎると失うもの

「結婚式で元を取りたい」という気持ちは自然なことですが、あまりにもこだわりすぎると、大切なものを見失ってしまうことがあります。
私自身、結婚式の準備中に「できるだけ費用を抑えたい」と思っていましたが、ある先輩花嫁さんに言われた言葉が心に残っています。
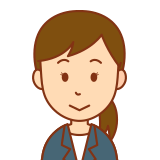
結婚式は費用対効果だけでは測れない価値があるよ
結婚式は人生の大切な節目を祝う場であり、大切な人たちと喜びを分かち合う特別な日です。
あまりにも「元を取る」ことにこだわりすぎると、思わぬところで後悔することも。
ここでは、「元を取る」ことにこだわりすぎると失ってしまうかもしれない大切なものについて考えてみましょう。
- 結婚式の質と思い出の価値
- ゲストとの大切な人間関係
- パートナーとの信頼関係
- 結婚式本来の目的と意義
費用面だけでなく、こういった目に見えない価値についても、ぜひ考えてみてくださいね。
結婚式の質と思い出の価値
費用削減のために演出や装飾を簡素化しすぎると、後になって「もっとこうすれば良かった」と後悔する可能性があります。
実際、私の周りでも「写真撮影を最低限にしたら、大切な瞬間が残せなかった」「装花を減らしすぎて、会場の雰囲気が寂しかった」という声をよく聞きます。
統計によると、6割以上のカップルが「演出や装飾を削りすぎた」と後悔しているんだとか。
特に、一生に一度の結婚式で重要なアイテム(花束や写真撮影など)を省くと、結婚式の思い出が味気ないものになってしまうリスクがあります。
友人のFさんは、予算を抑えるためにビデオ撮影をやめたのですが、「結婚式の感動的な瞬間を動画に残せなかったことが、今でも心残り」と言っていました。
費用面だけを考えると削ってしまいそうになるポイントでも、10年後、20年後に振り返ったときに「お金をかけてよかった」と思えるものは何かを考えることも大切です。
結婚式という特別な日の価値は、お金だけでは測れないことを忘れないでくださいね。
ゲストとの大切な人間関係
ご祝儀額を重視しすぎると、招待リストから経済状況が厳しい友人を除外するなど、人間関係にひびが入る可能性があります。
「この人からはいくらのご祝儀が期待できるか」という基準で招待客を選んでしまうと、本当に大切な人との関係を損なってしまうかもしれません。
私の知人Gさんは、学生時代からの親友を「お金がないだろうから」という理由で招待しなかったのですが、後になってその友人との関係が疎遠になってしまったと後悔していました。
また、引き出物や飲食の質を極端に落とすことで、ゲストに不快感を与えるケースも報告されています。
例えば、ある事例では、高価なドリンクコースを用意したにもかかわらず、ゲストからのご祝儀が予想より少なく、関係性に影響が出たというケースもあります。
結婚式は「おもてなしの場」であり、ゲストへの感謝を表す機会でもあります。
ご祝儀の額だけで人を判断するのではなく、これまでの関係性や思い出を大切にしたいものですね。
パートナーとの信頼関係
結婚式の費用分担を巡る意見の相違が、夫婦間のもめ事に発展することも少なくありません。
特に「衣装へのこだわり」と「料理のクオリティ」など、優先順位の違いが顕著になると、折半ルールの見直しが必要になるなど、調整が難しくなることがあります。
友人Hさん夫妻は、結婚式の費用をめぐって深刻な対立が生じ、
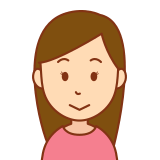
結婚式の準備中が人生で一番喧嘩した時期だった
と振り返っています。
「元を取る」ことにこだわるあまり、お互いの大切にしたいものを否定し合うようになると、結婚式という喜ばしい出来事が、ストレスの種になってしまいます。
結婚式の準備は、これから始まる夫婦の人生における最初の大きな「共同作業」とも言えます。
お互いの価値観を尊重し、話し合いながら準備を進めることで、より絆が深まる機会にもなるでしょう。
結婚式本来の目的と意義
黒字追求に集中するあまり、「おふたりの愛を祝い、感謝を伝える」という結婚式の本質を見失う危険性もあります。
費用対効果ばかりを気にすると、大切な人との時間を十分に楽しめなくなる可能性が指摘されています。
結婚式は、二人の愛を誓い、周りの人たちと分かち合うための場です。
「元を取る」ことにこだわりすぎると、結婚式の本来の目的を見失ってしまう可能性があります。
友人Iさんは「予算内に収めることばかり考えて、当日は会計係のようになってしまった」と反省していました。
結果的に、心に残らない結婚式になってしまうリスクもあるんです。
また、予測不能なリスクへの対応力も低下します。
ご祝儀収入を過度に当てにすると、ゲストの急な欠席やご祝儀額の予想外の低さにより、想定外の赤字が発生するリスクも。
実際、1人あたり3万円のコストをかけた式で、ゲストから2万円しかご祝儀がなかった事例も報告されています。
結婚式は、お金だけでは測れない価値があることを忘れずに、「ハレの日」らしい特別な時間を大切にしたいものですね。
結婚式の招待人数の最適解は?みんなはどう決めている?
結婚式の招待人数を決めるとき、「何人くらいがベストなんだろう?」と悩みますよね。
私自身も、最初は「できるだけ多くの人に来てもらいたい」と思っていましたが、予算や会場のキャパシティを考えると、やはり人数を絞る必要がありました。
結婚式の招待人数に「これが正解!」という答えはないのですが、多くのカップルがどのような基準で人数を決めているのか、そして地域によるトレンドの違いなども含めて見ていきましょう。
招待人数を決める際のヒントになるはずです。
- 全国平均と地域差
- スタイル別の人数目安
- 人数決定のポイント
- トレンドと失敗回避策
それぞれのカップルの状況や希望に合わせた「最適解」を見つける参考にしてくださいね。
全国平均と地域差
結婚式の招待人数の全国平均は約65名と言われています。
実際には50~90名くらいの範囲で設定するカップルが約半数を占めています。
ただし、この数字には地域によって顕著な差があるんですよ。
北海道や沖縄では100名以上の大人数式が一般的な一方、関西・東海地方では比較的少人数傾向にあります。
特に沖縄は親族・近隣住民を含め200名以上招くケースも珍しくありません!
私の沖縄出身の友人は、「親族だけで100人近くになった」と言っていました。
地域文化や風習によって「適切」とされる招待人数は異なるので、両家の出身地の慣習も確認しておくとよいでしょう。
特に親世代は「地元では〇〇人くらい呼ぶのが普通」という意識が強い場合があります。
意識のギャップを埋めるためにも、早めに話し合っておくことをお勧めします。
スタイル別の人数目安
結婚式のスタイルによっても、適切な人数は変わってきます。
リゾートウエディングなら10~30名程度が現実的です。
ゲストの移動負担を考えると、本当に親しい人だけに絞るカップルが多いんですよ。
友人Jさんは沖縄でのリゾ婚を選び、「移動距離が大きいから、無理に誘わずに20名だけで挙げた」と言っていました。
ゲストハウスウェディングなら50~100名程度が目安。
多くのゲストハウスは貸切で運営されており、一定の人数を満たさないと割高になってしまうことも。
レストランウェディングは20~40名程度がアットホームな雰囲気を保ちやすいです。
私の友人Kさんは「少人数だからこそゲスト全員としっかり話せた」と満足していました。
会場の最大収容人数より10~20%少なめに設定すると、ゆとりある空間を確保できるのでおすすめです。
人数決定のポイント
結婚式の人数を決める際に考慮すべきポイントはいくつかあります。
まず予算とのバランスが重要です。
費用相場は人数に比例して増えていきます。
10名以下なら100万円程度で済むこともありますが、60~80名だと380万~430万円、100名以上になると500万円以上かかることが一般的です。
予算超過を防ぐために、ゲストを「主賓」「必須」「希望」の3段階で優先順位付けする方法が効果的です。
私も実際にこの方法で招待リストを整理しました。
また、人間関係の優先度も考慮すべきポイント。
近年は「家族+親友」に限定する傾向が強く、10~30名の少人数式が増加しています。
職場関係者は招待しないケースも増えていますが、両家のバランス調整がトラブル防止の鍵となります。
私の知人カップルは「新郎側が多くて新婦側が少ない」という状況で、親戚同士で不公平感が生まれてしまったと後悔していました。
両家でなるべくバランスを取るよう心がけると良いでしょう。
トレンドと失敗回避策
最近のトレンドを見ると、多人数式(60~100名)と少人数式(~30名)に二極化している傾向があります。
多人数式のメリットは華やかさと社会的ネットワークの維持。
一方で、会場の制約や準備の負担が増えるという注意点もあります。
少人数式は費用の抑制とゲストとの深い交流が魅力ですが、招待漏れによる人間関係のリスクには注意が必要です。
友人Lさんは30名の少人数婚にしたところ、「呼ばれると思っていた」という友人からの冷たい反応があったそうです。
「呼べなかった理由」をしっかり説明することも大切かもしれませんね。
最適解は「式の本質的な目的」を明確にすること。
近年は「ゲスト全員と会話できる規模」「SNS映えする演出」を両立させるため、50~70名がバランス良い選択肢とされています。
式場選定時には、希望人数の1.2倍収容可能な会場を選ぶと、当日の柔軟な対応が可能です。
私たちも最終的に60名を招待し、会場は80名収容可能なスペースを選んだことで、ゆったりとした雰囲気で式を挙げることができました。
「結婚式で元取れる人数」のまとめ
結婚式で「元が取れる人数」について、いろいろな角度から見てきました。
費用対効果を考えることは大切ですが、結婚式は一生に一度の特別な日。
「元を取る」だけでなく、二人らしさや大切な人との時間を楽しむことも忘れないでくださいね。
この記事のポイントをおさらいしておきましょう。
- 10人以下の家族婚、30人程度の少人数婚、80人以上の大規模パーティーは黒字化しやすい
- 日取りや時間帯の工夫、会場選び、アイテム別の節約術で費用を抑えられる
- 「元を取る」ことにこだわりすぎると、大切な思い出や人間関係を損なう可能性も
- 全国平均は65.5名だが、地域性やスタイルによって適正人数は異なる
結婚式の招待人数を考える際には、予算だけでなく、二人の希望や家族との関係性、会場の雰囲などを考慮するのがベストですね。




















コメント