結婚式の費用を新婦側が出さない…そんな選択に迷いや不安を感じていませんか?
私もかつて同じ悩みを抱えた一人です。
「非常識って思われない?」「新郎側に甘えてる?」そんな気持ちで胸がいっぱいになりますよね。
でも、大丈夫!今の時代、結婚式の費用分担は本当に多様化しています。
私の経験や多くの先輩カップルの体験をもとに、この難しい問題について一緒に考えていきましょう。
結論から先にお伝えすると
- 結婚式費用の分担には「絶対的なルール」は存在しない
- 新婦側が費用を出さない選択も状況によっては十分アリ
- 大切なのは両家・カップル間の丁寧な話し合いと相互理解
- 経済状況や価値観の違いを率直に伝えることが良好な関係性への鍵
この記事では、実際のカップルの分担パターンや、新婦側が費用を出さない場合の具体的な関係性の保ち方まで、詳しくお伝えします。
ドキドキしながら準備を進める花嫁さんの気持ちに寄り添いながら、一緒に最適な解決策を見つけていきましょう!
結婚式の費用を新婦側が出さないのは非常識?甘えている?

「結婚式の費用、新婦側が出さないなんて非常識じゃない?」「新郎側に甘えすぎでは?」そんな声が聞こえてきそうで不安になりますよね。
でも、ちょっと待って!結婚式の費用分担について、実は固定的なルールなんて存在しないんです。
私も結婚準備のときは本当に悩みました。
友人からは「半分ずつが常識でしょ」と言われる一方で、「うちは新郎側が全部出してくれた」という先輩花嫁の話も。
混乱しますよね。
結婚式費用の分担について、主な考え方をまとめてみました。」
- 共同で築く家庭の始まりだから、費用も協力して負担するべき
- 対等な関係性のためには、経済的負担も均等に
- 招待客に応じて費用を分担するのが合理的
- 経済力に応じて分担するのがフェア
でも、これらはあくまで一般論。
実際の結婚式は二人だけのもの。
その準備や費用分担も、二人と両家の状況に合わせた「オーダーメイド」であるべきなんです。
「非常識」と感じられるケース
確かに、特別な理由もなく新婦側が費用を全く出さないと、周囲からは「非常識」と捉えられる可能性はあります。
私の友人の例ですが、単に「出したくないから」という理由だけで費用を一切出さなかった新婦がいて、新郎家族との間に大きな溝ができてしまったケースがありました。
長い結婚生活を考えると、スタート地点でのこうした印象は大切ですよね。
特に日本の結婚式では、「両家の結びつき」という意味合いもあるため、片方の家庭が全く関与しないというのは、確かに違和感を持たれることもあります。
でも、それはあくまで「特別な理由がない場合」の話。
実際には様々な背景があって、新婦側が費用を出せない・出さない状況というのは少なくないんです。
「甘え」ではない状況
「新郎側に甘えている」というのも、状況によります。
経済的事情で本当に出せない場合、新郎側の強い希望で費用を負担してもらう場合など、「甘え」ではなく「合意の上での役割分担」と捉えるべきケースも多いんです。
私の知人カップルでは、新婦が学生で収入がほとんどなかったため、新郎側が費用のほとんどを負担しました。
でも、新婦はDIYでウェルカムボードや招待状を作るなど、できる限りの貢献をしていましたよ。
お金だけが貢献ではない、というのも大切な視点です。
文化や価値観の違い
また、国や地域、家庭によって、結婚式の費用に対する考え方は本当に様々です。
海外では新郎側が全額負担するのが伝統的な文化もありますし、日本国内でも地域によって慣習が異なることもあります。
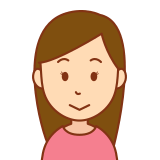
ウチの地方では男性側が出すのが当たり前
なんて話もよく聞きます。
こういった文化的背景や、両家の価値観の違いも尊重すべきでしょう。
結婚は二つの家族の文化が交わる瞬間でもあるんです。
私自身の経験から言えることは、「常識」と思われることより、二人と両家が納得できる形を見つけることの方が、ずっと大切だということ。
非常識や甘えと感じるのは外からの目。
それより大切なのは、二人の関係と将来の幸せです。
お金の問題は繊細ですが、だからこそ丁寧に向き合うことで、かえって絆が深まることもあるんですよ。
実際のカップルはどうしてる?よくある結婚式の費用分担パターン

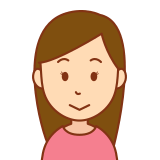
理想はわかるけど、実際のところみんなどうしてるの?
という疑問、すごくわかります!
私も結婚準備中は、友人や先輩花嫁に「費用どうしてる?」と聞きまくっていました。
恥ずかしながら、SNSの結婚関連グループでこっそり質問したこともあります(笑)。
そこで集めた情報から、実際のカップルがどのように費用を分担しているのか、パターン別にご紹介します。
これを知れば、自分たちに合った方法を選ぶヒントになるはず!
まずは、よくある分担パターンをまとめてみました。
| 分担パターン | 特徴 | 選ぶカップルの割合 | メリット・デメリット |
|---|---|---|---|
| 完全折半 | 総額を単純に2で割る | 約40% | シンプルで分かりやすいが、経済力の差があると負担感に差が出る |
| ゲスト人数比 | 招待した人数に応じて分担 | 約25% | 招待客が偏る場合に公平感があるが、共通ゲストの扱いが難しい |
| 一方が多く負担 | 新郎または新婦どちらかが多めに | 約20% | 経済力に差がある場合に現実的だが、気兼ねが生じることも |
| 項目別分担 | 衣装、会場費など項目ごとに担当を決める | 約10% | こだわりを反映しやすいが、計算が複雑になりがち |
| 二人の貯金から | 同棲中や共同口座からの支払い | 約5% | 一体感があるが、貯蓄の準備が必要 |
それぞれのパターンについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
完全折半による分担
最もシンプルで人気があるのが「折半」パターン。
総額を単純に2で割り、新郎側と新婦側(あるいは新郎と新婦本人)が同額を負担する方法です。
友人のAさんは
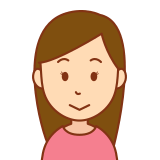
お互いに平等感があって、後々のもめごとがなかった
と言っていました。
ただ、収入に大きな差がある場合は、一方に大きな負担がかかることも。
私の知人カップルは最初「折半」で合意していましたが、実際に見積もりを取ったら予想以上の金額で、新婦側が「やっぱり厳しい」と言い出し、再交渉になったそうです。
事前によく話し合っておくことが大切ですね。
特に注意したいのは、「折半」と言っても、新婦のドレスや新郎のタキシード代などの個人の衣装代をどうするかでも変わってきます。
これらを含めて折半するのか、別立てで考えるのか、最初に決めておくと安心です。
ゲスト人数比による分担
ゲスト人数に応じて費用を分担する方法も、合理的でよく採用されています。
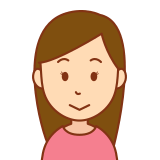
うちは新郎側が80人、新婦側が20人だったから、4:1の割合で分担したよ
という先輩カップルの話もよく聞きます。
特に、職場関係者や親族の数に大きな差がある場合は、この方法が納得感を生みやすいんです。
ただ、共通の友人をどちらにカウントするか、両家の親族をどう扱うかなど、線引きが難しい部分もあります。
私の場合は、共通の友人は「両方からの招待」として半分ずつカウントしました。
細かい計算は面倒ですが、明確なルールがあると安心感がありますよ。
一方が多く負担するパターン
収入の差や家庭の事情によって、どちらかが多く負担するケースも少なくありません。
「新郎の年収が新婦の3倍あったから、費用も3:1で分担した」というように、収入比で決めるカップルもいます。
また、「新郎側の家が裕福で、『全部出すから好きにしていい』と言ってくれた」という羨ましい(!)話も。
このパターンでは、少ない方が負担する側が「申し訳ない」と感じないよう、感謝の気持ちを伝えたり、他の形で貢献したりすることが大切です。
結婚生活は長い道のり。
今回は相手に多く負担してもらっても、将来は自分が支える番かもしれませんよね。
そういう長い目で見る視点も大事です。
項目別に分担するパターン
「衣装は新婦側、会場費は新郎側」というように、項目ごとに担当を決める方法も。
特にこだわりがある部分を自分が担当することで、満足度を高めることができます。
「料理にこだわりたい新郎側がその部分を多く負担し、装飾や写真にこだわる新婦側がその部分を担当した」という例も聞きました。
ただ、項目によって費用に大きな差が出ることもあるため、全体のバランスには注意が必要です。
予算オーバーのリスクも高いので、こまめな確認と調整が欠かせません。
二人の貯金から支払うパターン
同棲しているカップルや、結婚前から共同貯金をしていたカップルは、二人の貯金から支払うケースも。
「結婚式のために2年間コツコツ貯めた」という話も素敵ですよね。
このパターンだと「どっちがいくら」という考え方ではなく、二人で一緒に準備したという一体感が生まれるメリットがあります。
でも、十分な貯蓄期間が必要なので、すぐに結婚式を挙げたいカップルには難しいかもしれません。
実際のところ、これらのパターンを組み合わせたり、アレンジしたりするカップルが多いです。
大切なのは、お互いが「これで良い」と思える分担方法を見つけること。
どんな分担方法を選んでも、二人と両家の納得がある形が一番です。
結婚式の費用を新婦側が出さない選択がアリなワケ

「結婚式の費用、新婦側は出さない方がいい」なんて一般論は決してありません。
でも、状況によっては新婦側が費用を出さない選択も十分アリなんです。
私の友人にも、新婦側が費用を全く出さずに結婚式を挙げ、その後も円満に暮らしているカップルがいます。
彼女の場合は、新郎側のご両親が「息子の結婚式は親として全部出したい」という強い希望があったそうです。
最初は遠慮していたけれど、結局その申し出を受け入れたとか。
こういったケースのように、新婦側が費用を出さない選択がアリと言える理由をいくつか考えてみましょう。
経済状況の違い
最も一般的なのは、経済状況の違いによるものです。
例えば、新婦に十分な貯蓄がない、収入が少ない、あるいは家庭の事情で援助が期待できないといった場合。
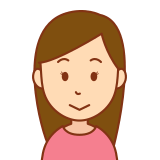
私はまだ学生で収入がほとんどないから、彼が全額出してくれると言ってくれた
という友人の話を聞いたことがあります。
無理に借金してまで費用を出す必要はありません。
経済的に余裕がない状況で無理をすると、結婚生活のスタートで大きな負担を抱えることになってしまいます。
また、新郎側の経済力が非常に高く、「全額負担させてほしい」という申し出がある場合も。
こうした申し出を素直に受け入れることも、一つの選択です。
感謝の気持ちを忘れずに伝え、別の形で貢献する姿勢を見せれば、お互いに気持ちよく準備を進められるでしょう。
結婚式に対する価値観の違い
新郎側が「盛大に祝いたい」という思いが強く、新婦はシンプルな式で良いと考えている場合もあります。
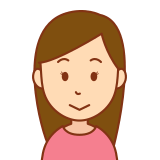
彼は大きな結婚式を希望していたけど、私はあまりこだわりがなかった。だから彼の希望通りの式にするけど、費用は彼が出す、という形になった
という話も聞きました。
理想の結婚式のイメージが異なる場合、こだわりが強い側が費用を多く負担するというのは、一つの合理的な解決策です。
また、親族関係の複雑さから、新婦側が式に消極的な場合もあります。
こうした場合も、新郎側が主導で進める代わりに費用も負担する、という選択があっても不思議ではありません。
文化的背景や慣習の違い
国際結婚や異なる文化背景を持つカップルの場合、結婚式の費用負担に関する慣習が異なることがあります。
「彼の国では男性側が結婚式の費用を全て負担するのが一般的」という文化もあります。
また、日本国内でも地域によって慣習が異なることも。
「東北出身の彼の家族は『男性側が出すのが当たり前』と言ってくれた」という話もありました。
こうした文化的背景や慣習を尊重することも、一つの選択肢です。
両家間の明確な合意
最も重要なのは、両家間で十分に話し合い、明確な合意があることです。
新婦側が費用を出さないという選択も、新郎側の自発的な申し出や、両家の話し合いの結果としてなされるべきもの。
一方的な押し付けや、黙って期待するのではなく、オープンなコミュニケーションが不可欠です。
私の友人は、最初は折半の予定だったけれど、新郎側のご両親が「長年貯めていたお金があるから、全部出したい」と強く希望されたそう。
何度も断ったけれど、最終的には「ありがたく受け取ります」と感謝の気持ちを伝え、受け入れたそうです。
その代わり、新婦側は新生活の家具や電化製品を多めに負担することで、バランスを取ったとか。
このように、結婚式だけでなく新生活全体を見渡した負担の分担を考えるのも良いアプローチです。
結局のところ、新婦側が費用を出さない選択がアリかどうかは、その背景や両家の合意次第。
「非常識」「甘え」というレッテルを気にするよりも、お互いが心から納得できる形を見つけることが、結婚生活の素敵なスタートにつながります。
各家庭の事情や価値観は様々。
自分たちにとっての「正解」を、相手を尊重しながら見つけていきましょう。
結婚式の費用を新婦側が出さない場合の関係性を保つ話し合いのポイント
いよいよ本題です。
結婚式の費用を新婦側が出さない場合、どうすれば新郎側との良好な関係を保ちながら話し合いを進められるのでしょうか?
私の友人たちの経験や、実際に上手くいったカップルの例をもとに、具体的なポイントをご紹介します。
正直に言って、お金の話ってどんな関係でも難しいものです。
特に結婚式という人生の一大イベントでは、なおさら。
でも、適切なアプローチで話し合えば、かえって二人の絆を深めるきっかけになるんですよ。
話し合いのポイントを表にまとめてみました:
| 話し合いのポイント | 具体的なアプローチ | 避けるべき態度・言動 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 率直に事情を説明する | 経済状況や家庭の事情を正直に伝える | 嘘をつく、曖昧にごまかす | 相互理解と信頼関係の構築 |
| 感謝の気持ちを示す | 言葉と行動で感謝を表現する | 当然と思う態度、無関心 | プラスの感情循環を生み出す |
| 代わりの貢献方法を提案 | 準備の手伝い、DIY、新生活費の負担など | 何も提案せず受け身の姿勢 | バランス感覚と公平感の創出 |
| 両家の親を交えた話し合い | 両家が顔を合わせる機会を作る | 親任せ、一方の親だけで決める | 家族間の結びつきと合意形成 |
| 将来の展望も含めた視点 | 結婚生活全体での役割分担も考慮 | 目先の話だけに集中する | 長期的な信頼関係の構築 |
それでは、これらのポイントを詳しく見ていきましょう。
率直に事情を説明する
まず最も大切なのは、費用を出せない理由や事情を率直に説明すること。
隠し事や遠回しな言い方は、かえって不信感を生みます。
私の知人は「実は今、学費ローンの返済中で…」と正直に伝えることで、新郎側の理解を得られたそうです。
具体的な金額や事情を包み隠さず話すことで、相手も状況を把握しやすくなります。
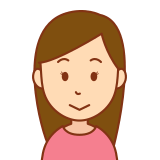
今の私の貯金はこれくらいで、毎月の収入はこれくらい。結婚式に出せるのはせいぜいこの程度…
というように、数字で示すとより明確です。
もちろん、単に「お金がない」だけでなく、「結婚式よりも新生活に費用を回したい」といった価値観の違いがある場合も、素直に伝えるべきでしょう。
正直な気持ちを伝えることは、これから長い結婚生活を共にする上での基本姿勢でもあります。
感謝の気持ちを示す
新郎側が費用を多く、あるいは全額負担してくれる場合、感謝の気持ちを言葉と行動で示すことが非常に重要です。
「ありがとう」の一言は簡単ですが、その気持ちがしっかり伝わるよう、繰り返し伝えましょう。
友人の例ですが、彼女は新郎側が費用を全額出してくれることになった際、手書きのお礼の手紙を新郎の両親に送ったそうです。
また、結婚式当日のスピーチでも、新郎側への感謝の言葉を忘れなかったとか。
こうした気持ちの表現は、金銭的な負担以上の価値を持つことがあります。
感謝の気持ちを示すことで、「お金を出してもらって当然」という印象を与えず、むしろ新郎側も「力になれて嬉しい」という前向きな気持ちになれるのです。
代わりの貢献方法を提案する
お金以外での貢献方法を自ら提案することも、大切なポイントです。
例えば、結婚式の準備を主導的に進める、DIYでウェルカムボードや席次表を作る、新郎側親族へのプレゼントを用意するなど。
私の友人は、新郎側が式の費用を負担する代わりに、新婚旅行は自分が計画から予約まで全て行い、費用も負担すると提案したそうです。
また、別の友人は、新生活の家具や家電は自分が多めに負担すると申し出て、バランスを取っていました。
こうした提案は、「お互いに出来ることで協力し合う」という夫婦の基本姿勢を示すことにもなります。
両家の親を交えた話し合い
可能であれば、両家の親を交えた話し合いの場を設けることも効果的です。
特に伝統的な考え方を持つ親世代は、「結婚式は両家の顔合わせの場」と考えている場合が多いもの。
直接顔を合わせて話すことで、誤解や行き違いを防ぎ、両家の親同士の関係も良好に保てます。
友人の例では、最初は新郎側の親が「新婦側が費用を出さない」ことに難色を示していたそうですが、新婦側の親が直接会って家庭の事情を説明したところ、理解を得られたとか。
また、親世代の知恵や経験が、思わぬ解決策をもたらすこともあります。
「実は私たちの時代も、男性側が多く負担するのが一般的だったのよ」という意外な一言で、状況が一変することも。
将来の展望も含めた視点
結婚式はあくまでスタート地点。
その先の長い結婚生活も視野に入れた話し合いが理想的です。
「今回は新郎側に多く負担してもらうけれど、将来子どもが生まれたら私が育児に専念したい」「今は私の収入が少ないけれど、数年後にはキャリアアップして家計に貢献したい」など、長期的な視点での役割分担を話し合うと良いでしょう。
結婚生活は長い旅路。
その中で、お互いが得意なことや状況に応じて、支え合っていくものです。
私の先輩夫婦は「結婚式は彼側が出してくれたけど、家のローンは私が多めに払っている」と教えてくれました。
時間の流れの中で、負担のバランスは自然と調整されていくものなのかもしれません。
これらのポイントを意識して話し合いを進めれば、費用分担の問題を乗り越え、むしろ二人の絆を深めるきっかけになるはずです。
お金の話は難しいからこそ、誠実に向き合うことで信頼関係が育まれるのです。
何よりも大切なのは、「私たちはチーム」という意識。
役割や負担が完全に均等でなくても、お互いを尊重し、感謝し合える関係が、幸せな結婚生活の基盤となるのではないでしょうか。
結婚式の費用を新婦側が出さないのまとめ
今回は「結婚式の費用を新婦側が出さない」という選択について、様々な角度から考えてきました。
非常識?甘え?そんな不安を抱えながらも、実は多くのカップルが自分たちの状況に合わせた費用分担を選んでいます。
結婚式は確かに人生の大きなイベントですが、その準備過程も含めて、二人の将来を築くための大切なステップ。費用の問題をきっかけに、価値観やお金の考え方について深く話し合うことで、かえって関係が深まることもあるのです。
この記事でお伝えしたように、新婦側が費用を出さない選択も、状況によっては十分アリ。大切なのは、経済状況や価値観を率直に伝え、お互いが納得できる形を見つけること。そして、費用を負担してくれる側への感謝の気持ちを忘れないこと。
また、結婚式はスタート地点に過ぎません。長い結婚生活の中では、様々な場面でお互いが支え合い、補い合っていくことになるでしょう。今回は新郎側が多く負担したとしても、将来的には別の形で新婦側が貢献できる機会も必ずあります。
私自身も結婚準備で悩んだ経験から言えるのは、「正解」はカップルの数だけあるということ。伝統や常識にとらわれず、自分たちにとってのベストな選択を見つけることが、素敵な結婚生活への第一歩になるはず。
どうか自信を持って、パートナーとオープンに話し合ってくださいね。二人の納得と幸せこそが、最も大切なことなのですから。




















コメント